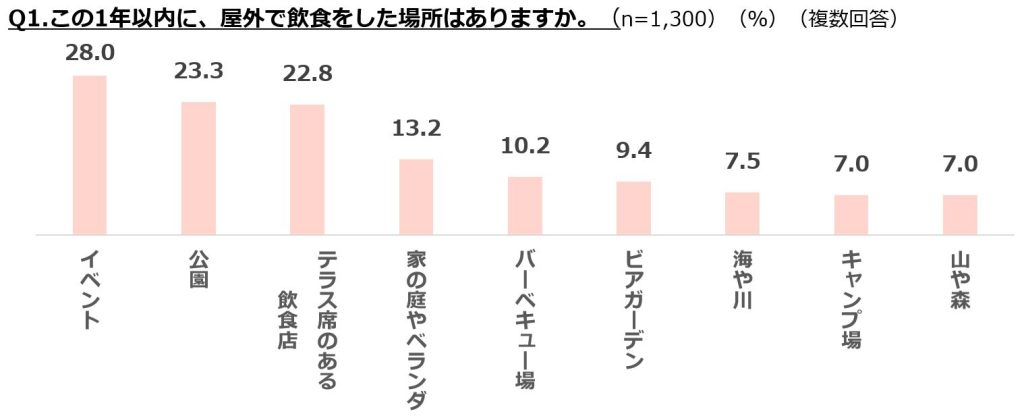-高橋監督からは芝居についてどんな指示が?
磯村 俳優陣には、まず好きなようにやらせてくれました。それから気になるところをディスカッションして一個一個、丁寧に作っていって。
生田 特に、姉妹を演じた2人とのやり取りではライブ感を大事にするというか、その瞬間を切り取るような感覚でしたね。彼女たちには台本を渡さず、現場で「これとこれだけ言って」といったやり方だったので、僕らもちょっとドキドキしながら…。
-お二人と関わる幼い姉妹を演じる子役2人がとても生き生きしていました。
生田 彼女たちが本当に素晴らしくて、ある意味、僕らが引っ張ってもらったような感じもあるよね。
磯村 そうですね。中でも、僕は一緒にアイスを食べるシーンがすごく好きで。あそこは子どもたちとの距離が少し縮まる瞬間で、温かな空気が流れていたんです。それを一連で撮る中で、僕はアイスの“当たり”を出さなきゃいけなかったので、タイミングを合わせる難しさも痛感しながら…。おかげで、アイスを食べ過ぎて頭が痛くなりました(笑)。
-お二人の熱演もあり、見応えのある映画でした。原作は30年前に発表された小説ですが、今の時代に映画化される意義をどう感じていますか。
生田 30年前の作品だとはあまり感じませんでした。いつの時代も、潤いとは真逆の立場に置かれている人たちが必ずいるんですよね。「太陽も空気もただなのに」というせりふがあるんですけど、なぜそれによって締めつけられる人たちが出てくるのか。そういうことを含め、普遍性のあるテーマじゃないかなと。劇中で僕が食べる、握り潰した“ヘビイチゴ”のように、苦味とちょっとした酸っぱさと、いろんな後味のする映画になったと思います。
磯村 特にコロナ禍を経た今の時代、そういう格差がより明確になってきた気がします。そういう意味では、この映画を作った製作陣の目が、ちゃんと時代を捉えていたんだろうなと。今見るのにふさわしい映画だと思います。
(取材・文/井上健一)