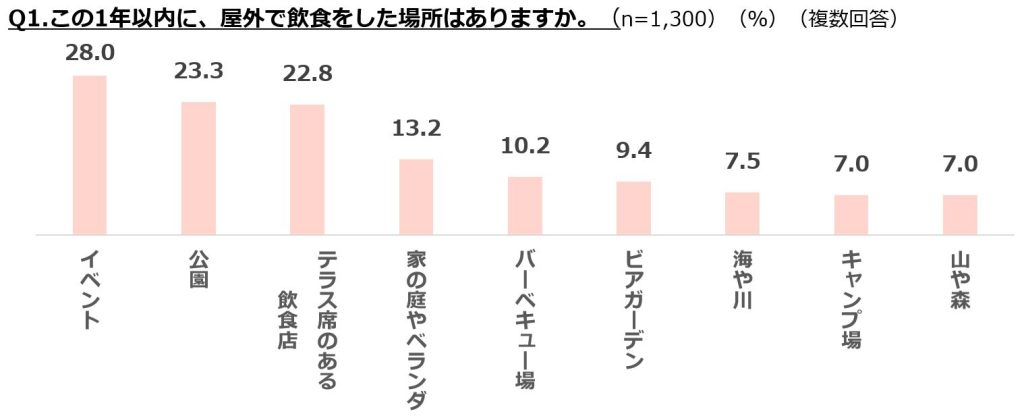人にとって、自由とは何だろう──。本書を読みながら、そんな問いが頭の中をぐるぐると巡った。
コミュニティ、会社、家族……人の生活は必ず何らかの集団と共にある。そこでは煩わしいことも、理不尽なこともある。それでも人は所属する集団の中でより善く生きようともがき、同時に、自由でありたいと願う。本書の“主人公”であるトヨタ自動車のチーフエンジニア、多田哲哉もそんな一人だ。
冒頭の場面がまず強い印象を残す。50歳を目前にした多田は犬を散歩させながら、人知れず会社への不満を吐き出す。かつてはチーフエンジニアを「製品の社長」と位置付けるほど技術職を尊重したトヨタ自動車の社風も、この頃は「チーフエンジニアの仕事は我慢することだ」と言われるまでに変容。自動車一筋の技術者には、それが我慢ならない。思い詰める夫の様子を、家族も心配そうにうかがっている。
そんな多田に突然下されたのは、願ってやまなかったスポーツカー作りという社命。ただしそれは、想像を超える苦難の道のりの始まりでもあった。
『しんがり』『石つぶて』『トッカイ』など、多くのノンフィクション作品で「会話の再現」に挑んできた著者。本作でも、意地をかけた者同士のやり取りには、息遣いまで伝わってくるようなスリルがある。うっかりすると、本作がノンフィクションであることを忘れてしまいそうだ。
多田はいわゆる立身出世の偉人ではない。気骨あふれる技術者、部下から「ジャイアン」というあだ名をつけられる上司、自動車ラリーのことになると我を忘れる少年のような夫。多様な顔を持つ市井の人間である。
ただ、彼が凡百の組織人と少し違うのは、集団の論理に易々と流されることを由としない点だ。それは多田だけではない。「ハチロクおたく」と呼ばれる部下の今井孝範も、多田を感服させる富士重工のエンジニア賚寛海も、多田が仰ぎ見てきた技術職の先達も、本書に登場する人々が何より大事にしているのは、おそらく自分自身に対して嘘をつかないこと。だから私たちは読み進めながら、「果たして自分は彼らのように生きられるだろうか」と何度も自問することになる。
終盤、大きな達成も挫折も味わった多田の退職後の姿が少しだけ描かれる。そこにいるのは、組織という拠りどころを失った寂しげな男ではない。いつ何時も自分らしくあるのを諦めなかったことで、小さくも確かな自由を掴み取った一人の人間だ。
その佇まいが、評者には何とも清々しく感じられた。
(瀬木広哉・編集者、ライター)