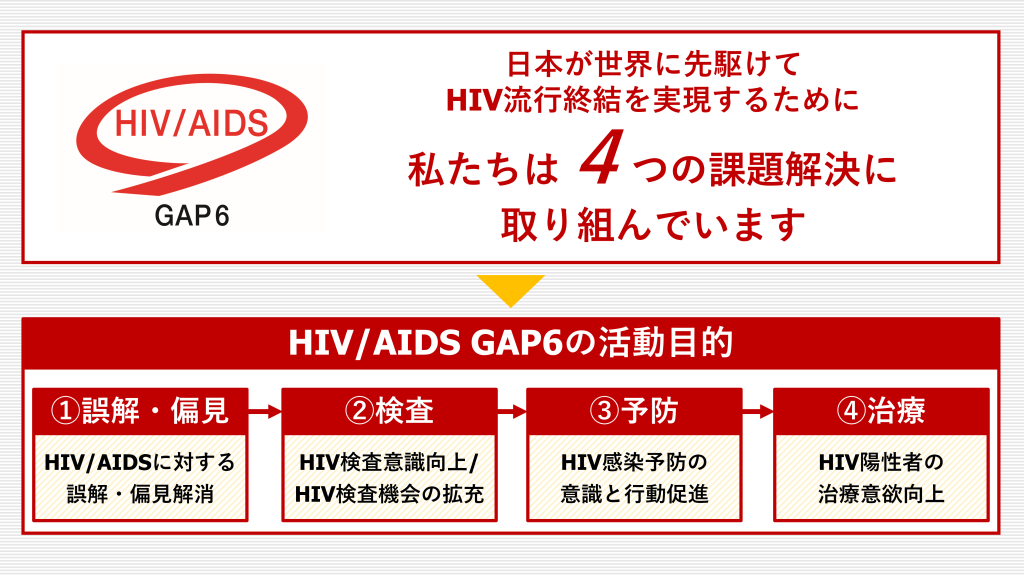バイオリニストのレオニダス・カヴァコスは、欧米と日本での知名度や評価の差が著しい演奏家の一人だ。1967年ギリシャ生まれの彼は、85年シベリウス、88年パガニーニなどの著名コンクールで優勝し、リサイタル、ベルリン・フィルやウィーン・フィルをはじめとする一流楽団との共演、室内楽、さらには指揮など、幅広く活躍している。
太さや強さと同時に柔らかさや透明感のある音、ダイナミックかつ繊細な表現、均衡を保った造形美とラテン的な情熱・・・彼はこれら全てを併せ持ち、楽曲の本質に沿った深い音楽を創出する。ただし、美音や技巧をひけらかさず、大仰なデフォルメや歌い回しはしない。その点が日本での認識の低さに結び付いているのであろう。派手さのない真の実力者、それがカヴァコスだ。
今回ご紹介するのは、彼がソロを弾いたJ・S・バッハのバイオリン協奏曲集。本作は通常の協奏曲集と異なる点が二つある。
一つは選曲。バッハのバイオリン協奏曲集といえば、第1番、第2番の2曲に二つのバイオリンのための協奏曲を加えるのが通例だ。だがここでは、第1、2番の他に、ニ短調、ト短調の二つの協奏曲が収録されている。ニ短調はチェンバロ(ピアノ)協奏曲第1番、ト短調は同じく第5番として知られる作品だが、原曲はバイオリン協奏曲とみなされている。本作ではそれらが復元して演奏されている。この選曲がまずは大きな妙味。両曲のサウンドはすこぶる新鮮で、バッハのバイオリン協奏曲の豊穣な世界を再認識させてくれる。

もう一つは、協奏曲で一般的なオーケストラではなく、小編成の「アポロン・アンサンブル」がバックを務めている点。カヴァコスと彼らは、この10月東京で本アルバムと全て同じ曲によるコンサートを行ったが、その際のバックは6人だった。すなわち1パート1人での演奏。それが室内楽的な感興を生み出す。ちなみに彼らは皆ギリシャ出身の気脈の通じた音楽家たち。このアンサンブルの妙も独自の魅力をなしている。
実際の演奏はモダン楽器でなされているが、ピリオド楽器や奏法(作曲当時の楽器や奏法)を踏まえた方向性。ストレートかつ純度の高い響きで、気品の漂う芳醇(ほうじゅん)な音楽が展開されている。速い楽章は精彩に富んだ鮮やかな演奏、遅い楽章はソロとバックの呼吸感に魅了されるし、全体の最後に置かれた「アリア(『G線上のアリア』の名で有名な曲)」が、「神々の練り歩きのような印象」(カヴァコス)を作り出す点や、随所で発揮されるチェンバロの自在の動きも聴きものとなる。
これは、最初より何度も聴くうちに感銘が深まるディスクでもある。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.46からの転載】

柴田 克彦(しばた・かつひこ)/音楽ライター、評論家。雑誌、コンサート・プログラム、CDブックレットなどへの寄稿のほか、講演や講座も受け持つ。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)、「1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集」(音楽之友社)。