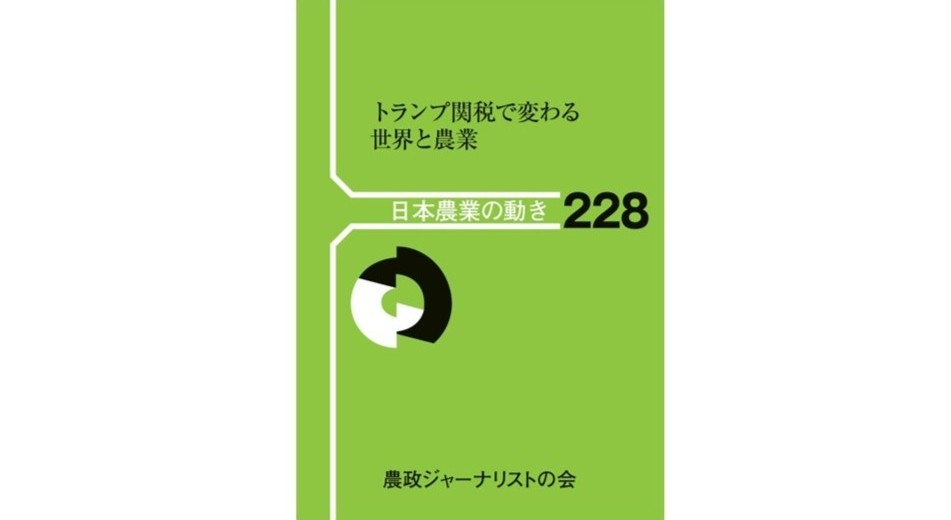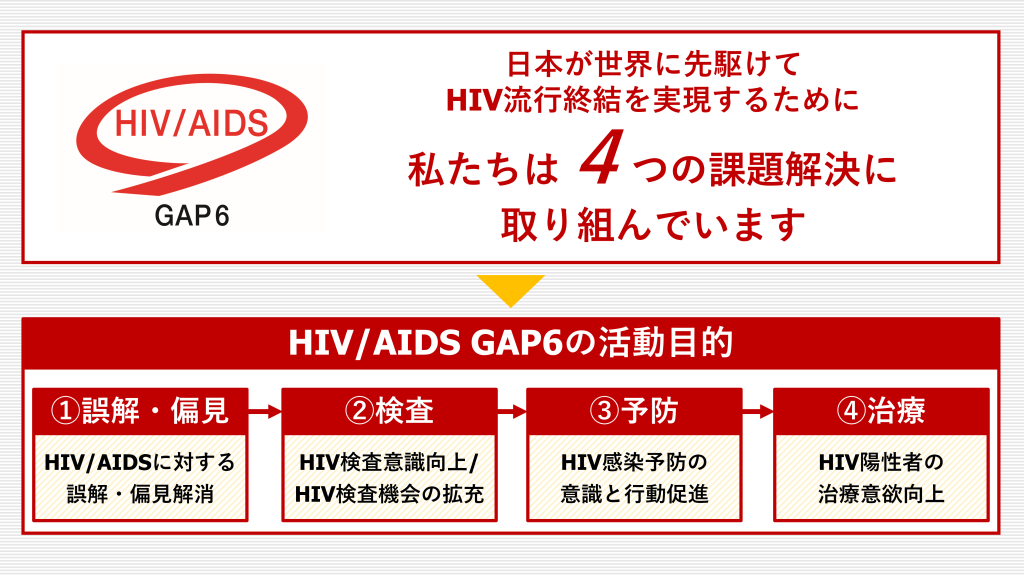新型コロナウイルス感染拡大防止で、主な各国・地域がPCR検査を精力的に進め、それによって確認された陽性者を一時隔離するという対策に取り組む中、日本だけは〝独自路線〟を歩んでいる。無料で、何回もPCR検査が気軽に受けられる態勢ができていない。その路線が奏功するのかどうか。早期に収束させた台湾の事例をまとめた書籍を紹介し、日本のあるべき対策について参考にしたい。(編集部)


新型コロナウイルス問題が起きてから、たくさんのコロナ関連本が書店に並んだ。「安かろう、悪かろう」ではないが、「早かろう、薄かろう」で、内容の乏しいものが多い。書名はどぎつく表紙はけばけばしい。「ポストコロナの世界」と、どうとでも書ける書名の本も目立つ。恐らく数時間の対談で手軽にまとめた本もある。何冊も掛け持ちしている評論家もいて、コロナ禍のような危機こそ彼らの書き入れ時なのだろう。とにかく世間の関心が続くうちに1冊でも多く売ろうという出版社の営業政策が見え見えだ。
そんな中、ここで取り上げる2冊は堅実な取材と長年の蓄積を発揮した数少ない書籍である。1冊は「なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか」(扶桑社新書、野嶋剛)で、もう1冊は「疫病2020」(産経新聞出版、門田隆将)だ。
台湾は世界で最も早くコロナ対策に成功した。徹底した検査、隔離、情報発信。それに電話相談やマスク販売情報の提供など総合的な対策を取った。隔離場所を勝手に離れると罰金も科した。「なぜ台湾~」には、その経過が詳しく描かれている。
読んでいて、当初は世界保健機関(WHO)情報に依存し続け、楽観的だった日本政府の対策がいかに劣っているかを改めて痛感した。台湾が素早く対応できたのは、中国と距離をとりWHOを信用しない蔡英文(さい・えいぶん)政権だから。蔡政権は中国の影響下にあるWHOにオブザーバーとしても参加もできず、締め出されている。ひどい話だ。昨年12月31日にWHOに「武漢で感染症による肺炎が発生した」とメールを送った。だが無視された。
野嶋は台湾の歴史的・社会的な背景をも描く。興味深かったのは日本が統治したとき、重点を置いた三つの政策に公衆衛生の改善が含まれていたことだ。台湾に多かった伝染病をなくすため、台湾総督府は総力を挙げた。
その伝統が今回のコロナ対策にも流れているのではないかと書いている。「感染症対策は台湾に学べ」ということだろうか。巻末に資料として、台湾と世界・日本の動きを時系列でまとめた記録がある。見開きなので比較できる。これを見れば台湾がコロナ対策を次々と打ち出していたころ、日本は何をしていたのかが、よく分かる。日本政府の後手に回った政策が一層際立つ。後日、中国の顔色をうかがうことなく台湾に調査団を派遣し、どのような対策を取ったのかを教えてもらい今後の糧とすべきだろう。
野嶋は朝日新聞社の元台北支局長で、約4年前にフリーとなって「台湾とは何か」(ちくま新書)を出版した。そこで台湾の政治や社会を鋭く分析しているのに感心したことがある。この新聞社の記者にありがちな「角度をつけた」癖がないというのが正直な印象だ。地味な新書だが、1人でも多くの方が読まれることを期待する。
「疫病~」はこれまで、さまざまな話題作を書いてきたジャーナリストによる本だ。
大きく分けて二つの柱からなっている。疫病をめぐって中国で何が起きていたのかということ。一方、日本ではどういう対応がされていたのかということ。その間に台湾での対策が挟み込まれている。興味深かったのは、中国・武漢にある病毒研究所(武漢ウイルス研究所)でどのようなウイルスの実験をしていたのか、ということが詳細に描かれていることだ。これまで新聞や雑誌で断片的に報じられてはきた。
しかし、これほど詳しい報告は読んだことはない。ここの研究者らが5年前に発表した学術論文を専門家の手を借りて読み解いている。中心人物は「コウモリ女」と呼ばれる女性の研究者だ。
もう一つの柱である日本国内でのコロナ対策をめぐる政策の舞台裏が生々しく描写されている。特に迷走の末に決まった10万円の給付金のてんまつが面白い。門田の主張は政府がダメだが、現場の人たちや国民の努力で被害を食い止めているというものだ。すべては現政権が悪いという「アベガー」という人たちとは一線を画していることは言うまでもない。強いて不満な点を挙げると、コロナ禍の恐ろしさをあまりにも強調し過ぎということ。感染者の95%が無症状か軽症であるとの見解もあり、重症はわずかである点に関心を払わない。
コロナ禍で問題なのは、過度に恐れて萎縮することで、適度に予防策をとれば普段の日常生活をすればいいと、一部ではあるがウイルスの専門家は言っている。(敬称略)
(北風)
(KyodoWeekly8月10/17日号から転載)