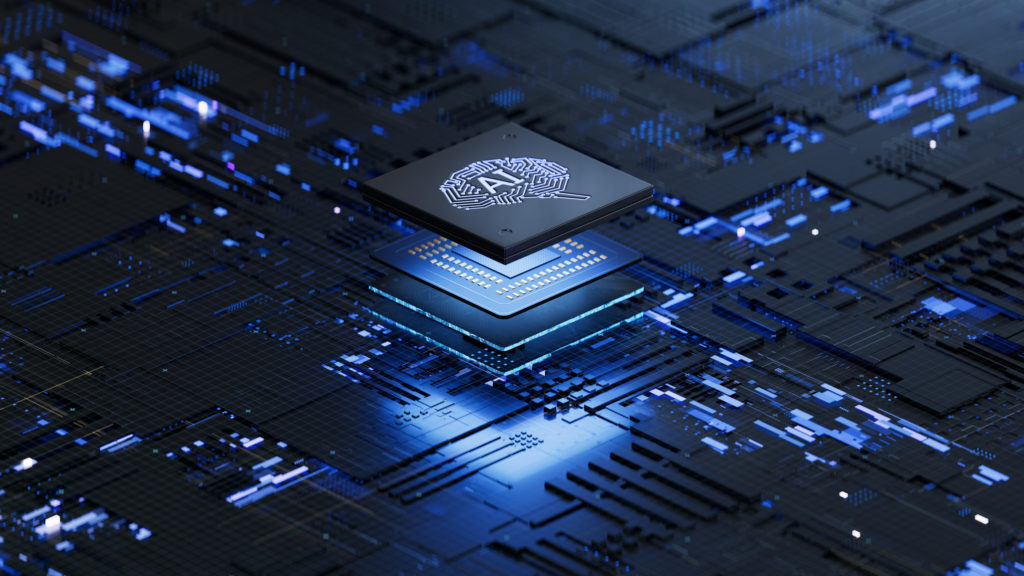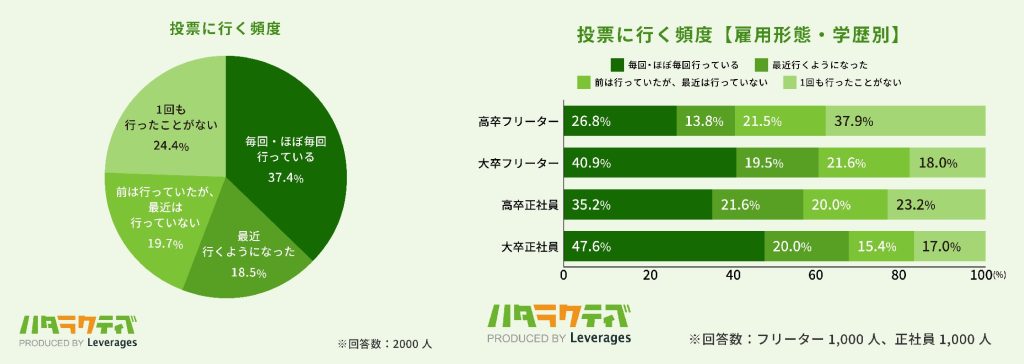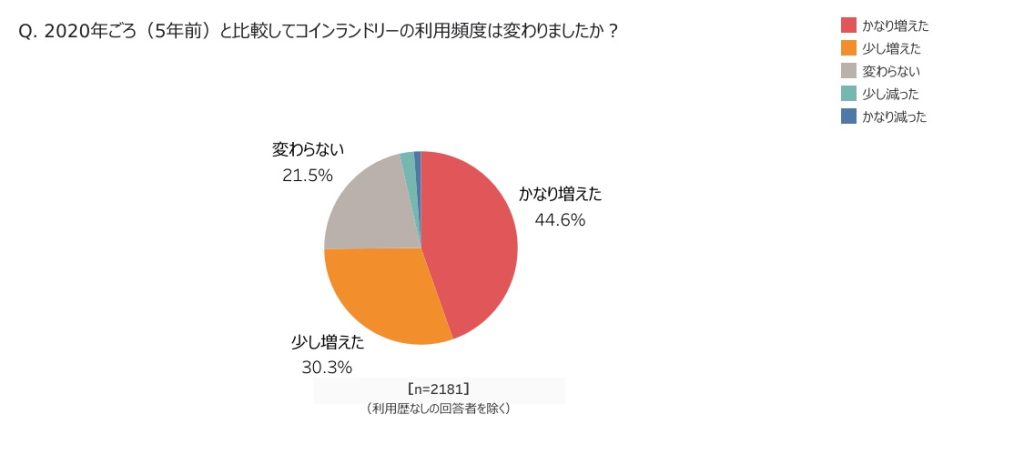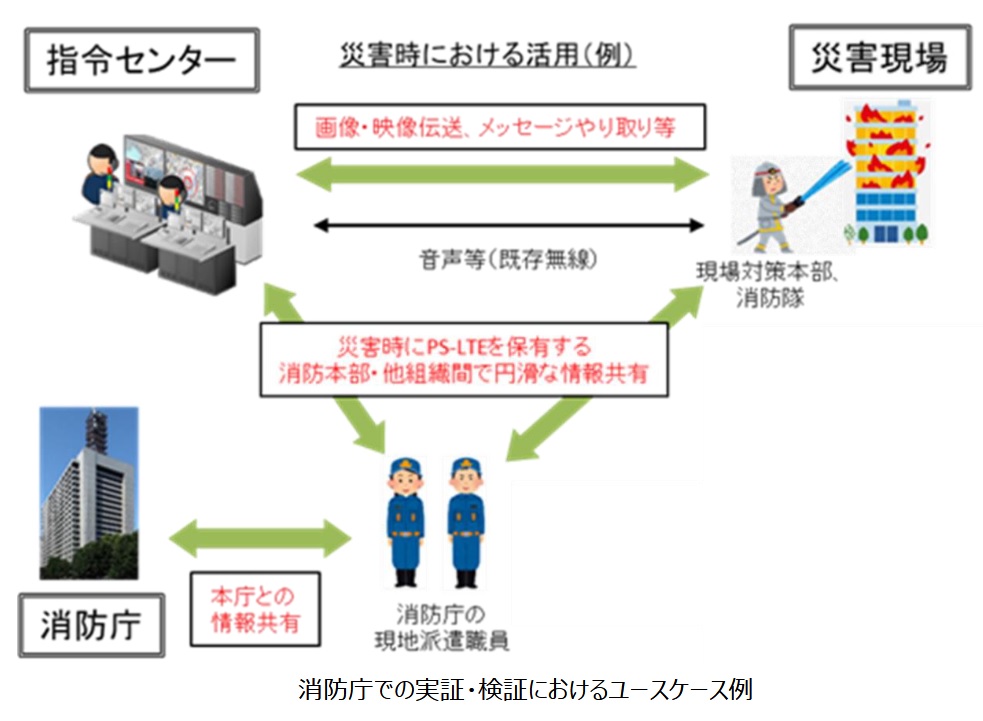自民党の副総裁や幹事長を務めた川島正二郎氏が「政界一寸先は闇」の名言を残したのは、もう半世紀以上も前のことである。政治状況が思わぬ展開になったり、想定外の方向に進んだりしたとき、今もこの名言が用いられる。2週間前、岸田文雄首相は改めてこの名言の重さと深さを、じだんだを踏みながらかみしめたはずである。
G7広島サミットの閉幕後、東京に戻る機内で岸田首相は上機嫌だったという。普段はあまり喜怒哀楽を出さないポーカーフェイスであるが、サミットを成功裡に終えた安堵感と満足感が笑みになって表れたのかもしれない。翌日の自民党役員会で岸田首相を見かけた者の一人は直観的に、「衆院を解散する覇気だ」と感じた。
だが、まさに好事魔多しである。その直後に「文春砲」がさく裂した。岸田首相の長男で政務秘書官を務める翔太郎氏が昨年末に首相公邸で親戚と忘年会を開き、公的スペースで大はしゃぎしていたことが写真付きで報じられ、サミット効果で期待された支持率上昇分は相殺されてしまった。当初、岸田首相は“厳重注意”で糊塗(こと)できると高をくくったが、「異次元の親バカ」といった痛罵に抗えず、わずか数日後に泣いて馬謖(ばしょく)を斬った。
昨年10月、岸田首相が若干31歳の長男を秘書官に起用し、世論から「縁故採用」「公私混同」といった批判を浴びた。今年1月の外遊の際の観光や買い物でも、翔太郎秘書官は週刊誌をにぎわせたし、官邸内の重要な情報を一部のマスコミに漏らしているのではないかとの嫌疑もかけられた。「どれだけ甘く見ても、これまで目立った功績はなかった」(自民中堅議員)というのが、関係者に共通する見方である。
どんな親でも子はかわいいものである。岸田首相は「獅子の子落とし」とは逆に「温室栽培」を試みたが、“養育係”もつけず、単なる箔付けのために翔太郎氏を秘書官に抜擢した結果、皮肉にも溺愛する息子の将来に傷をつけてしまったことは否めない。半年も前の忘年会の記事であるにもかかわらず、与党内にでさえ翔太郎氏、さらには岸田親子をかばう者が皆無に等しかった理由を、岸田首相はまず考えるべきである。
しかし、今回の“秘書官更迭劇”の根はもっと深いと考えられる。4月の衆院山口2区補選で岸信千世氏が相手候補に猛追されたように、国民の多くは政治家の公私混同や特権意識、世襲に対して厳しい目を向けている。経済格差の拡大や物価高も手伝って、「こうした不満は10年前よりもはるかに大きくなっている」(自民閣僚経験者)というが、この深刻な状況は岸田首相の耳には入っていないし、「岸田ノート」にも書かれていないようである。
さらに、数字だけを見れば、確かに内閣支持率は回復してきているが、たとえば安倍晋三政権のときとは強弱にも濃淡にも大きな違いがある。故安倍首相を毛嫌いする人もいたが、熱烈に愛する人も多かった。つまり、敵も味方も多かったのであるが、岸田首相の場合、たとえ表面上は支持をしても、感情を伴わない「消極的支持」である場合が多い。いわば人のいい“通りすがりのオジサン”に近いのであるが、支持率の回復で岸田首相本人は“愛されキャラ”になったと勘違いしたようである。
岸田首相が自民党や公明党、あるいは一部の野党の声に耳を傾けるのは結構なことである。しかし、青臭い書生論ながら、民主主義国家において最も重視されるべきは国民の“声なき声”にほかならない。そこに「聞く力」を発揮せず、自身の総裁再選のためだけに衆院の解散総選挙に挑めば、たとえ野党が不甲斐なくても、早晩、手痛いしっぺ返しを食らうことになるのではないか。
間もなく会期末。岸田首相の学習効果が試される。
【筆者略歴】
本田雅俊(ほんだ・まさとし) 政治行政アナリスト・金城大学客員教授。1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。