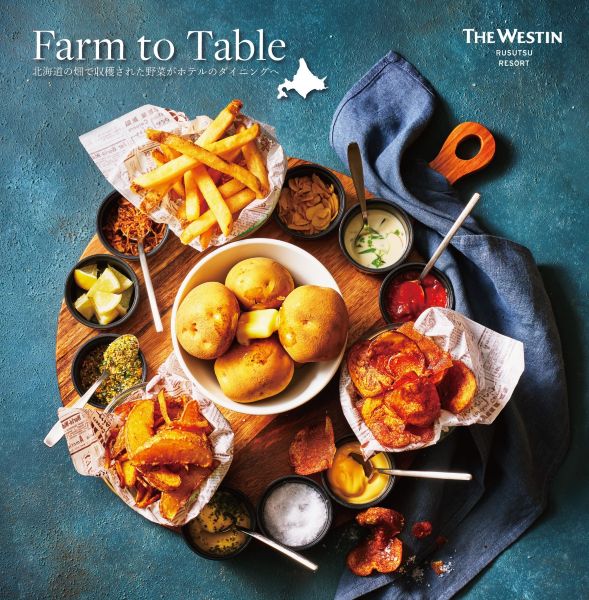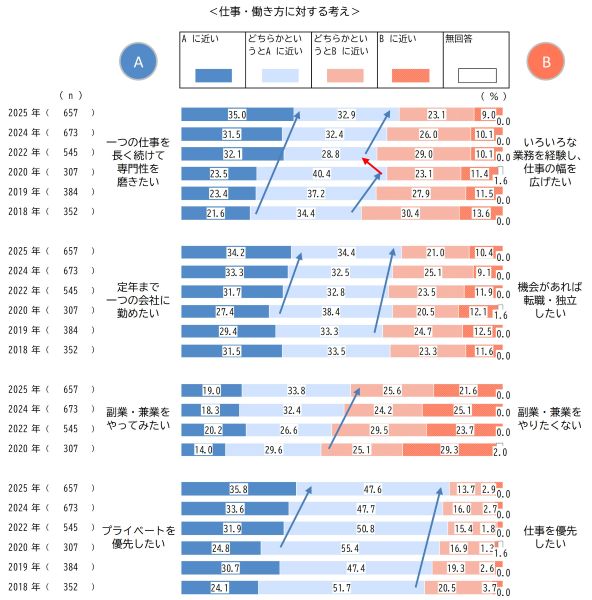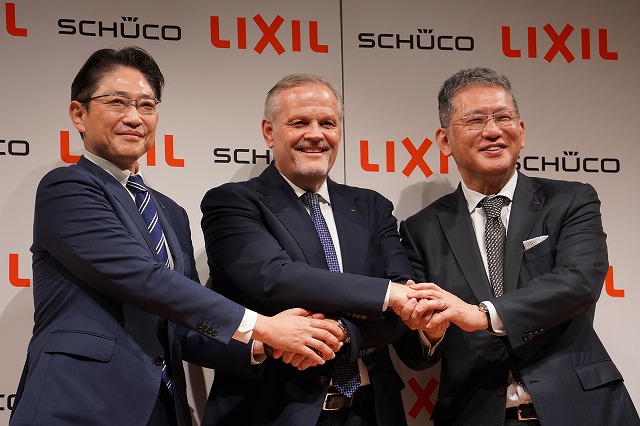振り返ってみればこの回、正信は家康を動かす言葉をいくつも放っている。序盤、徳川の内情を知る数正が秀吉の配下となったことを受けて「とりあえず、わが方の陣立てもすべて改めるべきかと。この際、武田の軍法を倣っては?」と軍の改革を提案。
さらに中盤、ひそかに数正の動向を探らせると、「これといった働きは何ひとつ聞こえてきませぬ」と報告。数正が“飼い殺し”になっていることを見抜き、家康の下から数正を奪うことで、戦力低下を狙った秀吉の真意が明らかになる。
この回に限らず、本能寺の変を知り、“伊賀越え”で三河に戻ろうとした家康たちの前に突然現れ、窮地を救った第29回、小牧・長久手の戦いで岡崎を攻めようとする秀吉軍の“中入り”を見抜いた第32回など、数多い徳川家臣団の中でも、正信は他と一味違った振る舞いで家康を支え、独自の存在感を放っている。それは、正信が家康の軍師的な立場にあるためだが、それだけではないようにも思える。
みそ田楽を頬張りつつ、斜に構えて家康に数正の動向を報告する際の余裕ある態度(あるいは図々しさ)。やや離れた位置から秀吉への臣従を巡る家臣団の議論を眺め、的確に言葉を放つ際のキリっとした表情…。
その変化球を多投するようなつかみどころのない芝居こそが、正信の唯一無二の存在感の源といえるのではないだろうか。そこには、「平清盛」(12)で大河の主演を1年間経験した松山だからこそ生まれる味わいというか、余裕のようなものすら感じられる。そしてそれが、家康役の松本をはじめとする共演者の芝居まで際立たせ、結果的に物語がより豊かになる。例えばこの回の序盤、軍の改革を提案した際の血気盛んな直政役の板垣とのやり取りも、相手が松山でなければ、かなり印象が違っていたはずだ。
そんな松山=正信が、これからいかに家康の天下取りを支えていくのか。期待を込めて見守っていきたい。
(井上健一)