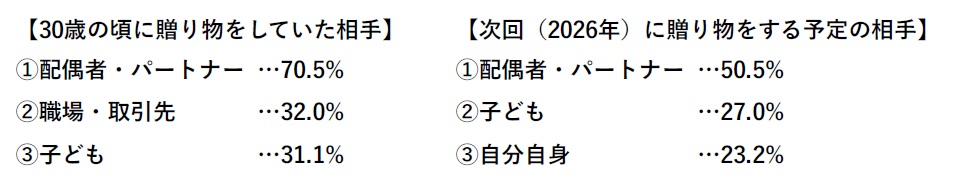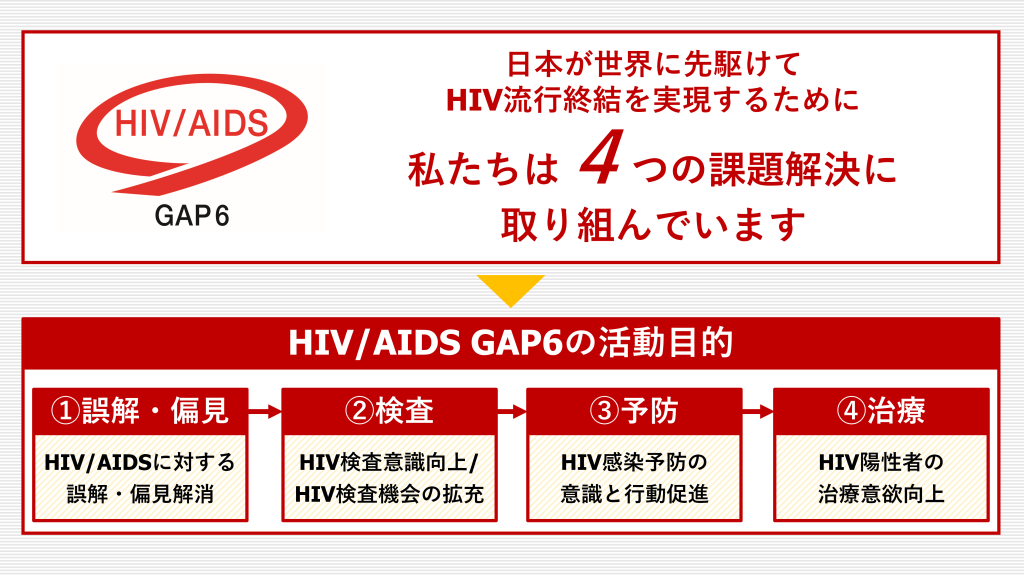-結果として戦争に協力をしてしまうという、理不尽で葛藤の多い役だったと思いますが、どのようにして自分の中に落とし込んでいったのでしょうか。
集中することでした。実際に起きたことでも、当時の人はその先に戦争が起きるとは思ってもいなかったと思うんです。でも演じている僕らはその先に起きることを知っています。だから、起きることの真実に対して集中する、そこに全力を傾けるということを考えながら人とも対峙していたし、いろんなシーンで常に集中していました。
-言葉を発して他人に影響を与えるという意味では、アナウンサーも役者も共通点があると思いますが、和田さんに共感する部分はありましたか。
共通点があるからこそ魅力を感じたんだと思います。やり方が微妙に違うかもしれないけれど、自分の中に入れてそれを出すという部分では通じるところがあると思います。和田さんは電車の中とかでもブツブツしゃべっているんです。僕もせりふを覚える時にはブツブツしゃべっている(笑)、その辺は似ているというか一緒だなって。和田さんは、飯を食っていても、人と会っていても、何をしていても、アナウンスをするということが常に頭の中にある。僕も常に自分のせりふを覚えなきゃいけないという思いがある。そこは何か一緒だなという感覚があります。
-今回演じるに当たって、「言葉」について深く考えましたか。
そうですね。アナウンサーは伝える仕事なので、自分からどういう音を出すのか、演出の一木さんとも相談しましたし、原稿を読むシーンでも、当時の癖というか、そういうことも練習させてもらいました。特に僕は舞台をやる時は、どれぐらいの声でお客さんに届くのか、お客さんの手前で止めるのか、直接表現するのか、その先に行かせるのかということは意識してやっています。今回は映像でしたが、言葉をどう伝えるのか、表現するのかということを探っていたような気がします。
-「これは終わったことではない」という森田さんのコメントがありましたが、それはどういうところから感じたのでしょうか。
今の日本は、ある意味、平和で安心な国という感じですけど、海外では戦争が起こっているし、日本も明日はどうなるか分からないという意味もあります。それと、今回は言葉というものが大きなテーマになっていますから、今も言葉で人を傷つけたり、傷ついたりする人もたくさんいると思うので、決して昔話ではないと。僕と同世代の人や若い人たちももっと言葉について考える必要があるんじゃないかと思いました。
-森田さんにとって、この作品はどのようなものになりましたか。
この役を演じられたことは、僕にとっては宝物です。それは個人的な感情です。自分の心が動く作品や役に出合えることはなかなかないと思うので、そういう作品に出合えたことは財産だと思います。自分の中ではもう終わった役ではありますが、こうして映画になると1人でも多くの方に見ていただきたいという思いが湧いてきます。
(取材・文・写真/田中雄二)