農林中央金庫は9月3日、昨年8月に設立した「インセッティングコンソーシアム」(共同事業体)に16社が新たに参画したと発表した。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構をテクニカルパートナーとして迎えたことも公表した。コンソーシアムは、食品の生産から加工、流通、消費までつながる一連のバリューチェーン(食農バリューチェーン)全体の脱酸素化やネイチャーポジティブを目指す事業体で、すかいらーくホールディングス、ニチレイフーズ、TOWING(トーイング)とともに設立していた。新たな社が加わり、バリューチェーン全体に広く接点を有する農林中央金庫がハブとなって事業体として本格的な活動に入る。
今年7月に、新規参加の16社も参加して1回目の会合を開催した。全体会合では、取り組みの報告に加え、農業分野の脱炭素と政策動向・国際動向に関する基調講演、課題解決に取り組む企業に技術紹介を実施。メンバー間での関係構築も活発に行われ、連携を強化する貴重な機会となったという。
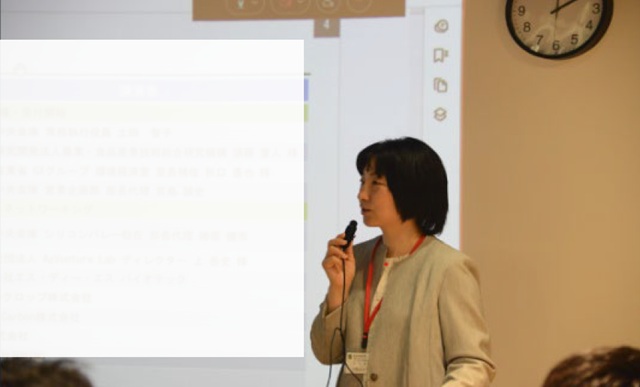
今後は、産品を消費者に届けるまでの環境負荷の軽減を国内で進めていくために、国際的な議論を収集。共同事業体内での「米穀」「畜産」「土壌」の3つのワーキンググループを設立し、国内の生産現場の実情や食農関連企業の商慣行に沿った「国内版ガイドライン」の策定を進めていく。これらを通じて、企業単独では対応が難しい、原材料調達による間接的な温室効果ガスの削減を生産現場との連携で促進していく。共同事業体への賛同企業・団体等の参画も呼び掛けている。
国内では、インセッティング(自社のバリューチェーンの中で温室効果ガスの削減に取り組むことで、その効果をバリューチェーン全体で享受する取り組み)の概念は十分に浸透していないという。特に農林水産業を調達先とする食品メーカーや小売などの食農関連企業では、農業生産上での温室効果ガス削減や自然への影響の低減が求められる中で、食農関連企業における農業者の生産状況の理解や投資・支援のための接点構築に関わる動きは十分に拡大していないという。インセッティングの実装が不可欠でありながら、トレーサビリティ(製品や原材料の生産・加工・流通・販売などの過程を記録し、追跡できるようにする仕組み)の不足などが背景になっているという。
環境負荷軽減対策を促進していくためには、関係する幅広い利害関係者が連携し、農法や技術・資材について検討し、導入・普及を支援していく仕組みが重要となる。今回、新たな賛同企業・技術面でのパートナーを迎え、その連携を一層強化して、脱炭素やネイチャーポジティブ(生物多様性の損失を止めて回復させること)に向けた投資支援が、国際基準で認められることを目指していくとしている。
【今回新たに参加した社】
エス・ディー・エス バイオテック▽カゴメ▽兼松▽キッコーマン▽クオンクロップ▽サントリーホールディングス▽スターゼン▽全国農業協同組合連合会▽日清食品ホールディングス▽バイオセラー▽ファミリーマート▽フェイガー▽明治ホールディングス▽森永乳業▽DSM▽Green Carbon




























