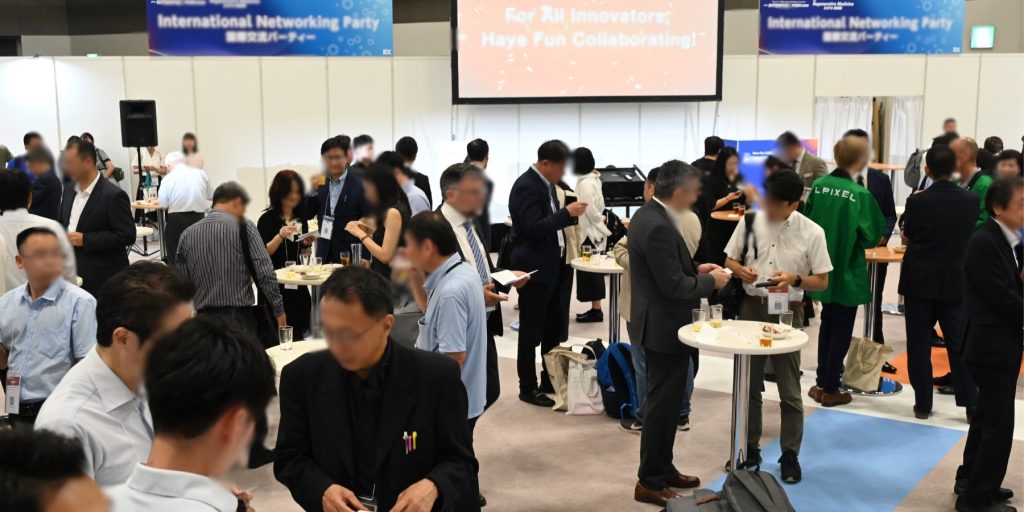弁当作りを通じて子どもたちを育てる取り組み「子どもが作る弁当の日」に関わる大人たちが、自炊や子育てを取り巻く状況を見つめる連載コラム。「弁当の日」提唱者である弁当先生(竹下和男)が語る、子どもを台所に立たせることに否定的だったある女性の話——。
親が毎日の食事を作るのは、本当に当たり前のことなのでしょうか?
当たり前だから苦もなく食事を作っている人がいる一方で、最近は、それができない親に対して「親が毎日の食事を作るのは当たり前だ」と責めたり、あるいは「当たり前だから」と感謝できない子どもも見受けられるようです。
この「毎日の食事は親が作って当たり前」という感覚は、現在多くの日本人が自然に身に付けている感覚の一つだと思います。
私の校長時代にも、そういう女性職員がいました。彼女には3人の子どもがいましたが、子どもを台所に立たせることには否定的でした。
◆
彼女は建設会社で働く夫と共働きでしたが、とりあえず家事の全ては彼女が一人でしていました。彼女はそれを当たり前と思っていました。
というのも、彼女の父親は中学3年生のときに他界し、掃除、洗濯、炊事のほとんどを彼女が一人でこなしてきていたのです。夜遅くまで保険会社の仕事をしている母親のことを思うと、それは仕方ないことでした。
高校3年生のときに母も逝きました。学費は自分で払うことにして短大に進学すると母と約束していたけれど、高卒で就職しました。その時、「弟は大学まで行かせる」と心に決めていました。
弟が大学進学を決めた時、不思議なことに、自分にも子育てができそうに思えていました。夫と結婚して子どもを授かるたびに、「育てられる」という思いが湧いてきました。
長女、次女、長男を育てながら、ずっと子どもに家事はやらせませんでした。父が逝き、母が逝ってからの「家事の大変さ」を、「両親がいない」というつらさが覆い隠していたのでしょう。結婚して子どもが増えるに従って「家事の大変さ」は大きくなっていったのに、「子どもがいる」といううれしさの方が勝っていました。
理由は他にもありました。子どもにさせるより、自分でした方が早いのです。しかも、家事をしていたために自分が持てなかった「楽しい時間」をわが子に与えられている、という喜びもありました。自分が両親にしてもらえなかったことを、わが子にしてやれているという誇らしさもあったのでしょう。
◆
そんな時、彼女は学校のPTA研修会で、「子どもを台所に立たせよう」という講演を聴きました。彼女は号泣しました。『はなちゃんのみそ汁』の話です。乳がんの再発で苦しんでいる母親が4歳児の娘を台所に立たせる話でした。
「小学校に上がる前から家事を教え込まれるなんて、女の子がかわいそうだ」
彼女は最初、そう思いました。母親が逝ったあと、父親のみそ汁もはなちゃんが作っていました。児童虐待に思えました。父親が作ってやればいいのに、と思いました。
ところが、はなちゃんが小学校を卒業するころには、料理本まで出版していました。わが長女も小学6年生でした。びっくりしました。まったく台所に立たせずに育ててきていました。
さっそく3人の子どもを台所に立たせ始めました。すると、子どもの発達に合わせて仕事を体験させる段取りが次々と見えてくるのです。子どもたちは自分にできる仕事を任されて、仕事をすると褒められ、感謝されるという繰り返しになりました。
長女は仕事ののみ込みが早く、妹弟より手早いので、「お姉ちゃんはすごいね」と褒めました。下の2人は「姉に追いつけ、追い越せ」の表情で、見よう見まねで仕事を覚えていきました。彼女の台所仕事は断然、楽になってきました。
ある寒い日の夕刻のことです。一日中、屋外の現場仕事だった夫が帰ってくるなり、「あったかい鍋を食べたい」と言って台所に入ってきました。夕食後に持ち帰った仕事に取り掛かるつもりだった彼女は、カレーを作る準備を整えたところでした。
「今からはダメ! もうカレーを作っているんだから」と答えると、夫は「仕事中、あったかい鍋料理だけを想像しながら働いてたんや。頼む、鍋にしてくれ」と譲ろうとしません。「ごめん。それだったら、自分だけの鍋料理を作って」と言い放ちました。
料理に注文をつけてくることのない夫だから、よほど鍋料理が恋しかったのでしょう。でも彼女もお尻に火が付いた状態だったので、譲れませんでした。「そんなこと言われても、俺、自分で作れんし…」夫は食卓のイスにへなへなと座り込みました。
その時、夫の肩をポンポンとたたいた子がいました。小学1年生の長男です。
「大丈夫、ぼくが教えてあげる」
その時の夫の顔を、彼女は一生忘れないと思いました。
「お母さん、休んでていいよ」と長男が言うと、宿題をしていた姉2人が、「一緒に作ろう」と言って台所に入ってきました。
長男は戸棚から土鍋を出してきて、水を張ると昆布を沈めました。長女は白菜やネギをザクザクと切り始め、次女は豆腐やタラや鶏肉の下ごしらえを始めました。皿に食材が並べられ、次々と土鍋の中に入れ始めたころには、5人家族全員が食卓に着いていました。
寄せ鍋は作りながら食べる楽しさもあります。もしかすると、カレーよりも早くに夕食が始まりました。
鍋からもうもうと上がる湯気越しに見える家族の顔を見ながら、幸せを感じていました。ユズの香りたつ出汁に浸った白菜やネギは甘く、タラや鶏肉はうまくて温かく、何よりのごちそうでした。そして彼女は、自分一人で作った寄せ鍋よりも、間違いなくおいしいと思いました。
いよいよ「シメ」に入る時、夫の「雑炊はどうすればいい?」に反応し、鍋奉行になったのはやっぱり長男でした。人数分のご飯をボールで軽く洗って鍋の中に納めると、溶き卵を回しがけして、ふたを閉めました。
待つこと数分。夫がふたを持ち上げると、一瞬にして濃い霧のような湯気が立ちあがり、鍋の中に白身と黄身がかすかな縞模様を描いた雑炊が見えました。
「うわあ、おいしそう」
◆
炊事は、親がいれば「やってもらえるのが当たり前」と思っていました。両親とも亡くなった高校生の時、弟の母親として生きることになり、自分が炊事をして当たり前でした。子育てが始まると、親の自分がいるのだから、自分が炊事をして当たり前でした。「子どもを台所に立たせよう」という考えは、自分の家庭には必要ないことだと思っていました。
でも自分も、はなちゃんのお母さん(千恵さん)のように、病気で若死にする可能性もあります。彼女は、千恵さんが、心を鬼にして幼いはなちゃんを台所に立たせた気持ちが分かるようになっていました。
「思い立ったが吉日」といいます。彼女の3人の子どもは、はなちゃんよりも台所に立ち始めたのが遅かったけれど、機会あるごとに彼女の教えを身につけていっています。
千恵さんのような焦りや悲壮感はなく楽しい仕事として、子どもと一緒に台所に立つことができていると思えるだけで、幸せな日々に感謝しているそうです。
竹下和男(たけした・かずお)
1949年香川県出身。小学校、中学校教員、教育行政職を経て2001年度より綾南町立滝宮小学校校長として「弁当の日」を始める。定年退職後2010年度より執筆・講演活動を行っている。著書に『“弁当の日”がやってきた』(自然食通信社)、『できる!を伸ばす弁当の日』(共同通信社・編著)などがある。
#「弁当の日」応援プロジェクト は「弁当の日」の実践を通じて、健全な次世代育成と持続可能な社会の構築を目指しています。より多くの方に「弁当の日」の取り組みを知っていただき、一人でも多くの子どもたちに「弁当の日」を経験してほしいと考え、キッコーマン、クリナップ、クレハ、信州ハム、住友生命保険、全国農業協同組合連合会、日清オイリオグループ、ハウス食品グループ本社、雪印メグミルク、アートネイチャー、東京農業大学、グリーン・シップとともにさまざまな活動を行っています。