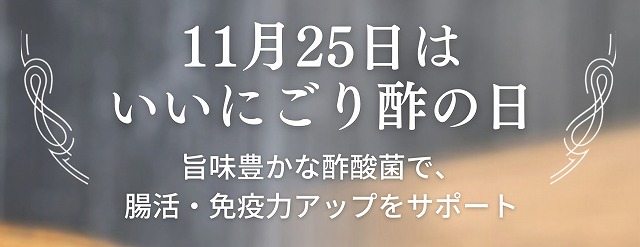『ワース 命の値段』(2月23日公開)

2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロを受け、米政府は被害者と遺族の救済を目的とした補償基金プログラムを立ち上げる。
その特別管理人を任された弁護士のケン・ファインバーグ(マイケル・キートン)は、独自の計算式により、個々人の補償金額を算出する方針を打ち出すが、被害者遺族が抱えるさまざまな事情と、彼らの喪失感や悲しみに接する中で、次第に矛盾を感じ始める。
政府が掲げる、約7000人の対象者の80%の賛同を得る目標に向けた作業が停滞する一方で、プログラム反対派の活動が勢いづいていく。期限が迫る中、苦境に立たされたファインバーグはある決断を下す。
同時多発テロ被害者の補償金分配を束ねた弁護士と遺族たちとの2年間を、実話を基に映画化。主役のキートンに加えて、反対派のリーダー役でスタンリー・トゥッチ、ファインバーグのビジネスパートナー役でエイミー・ライアンらが共演。監督はサラ・コランジェロ。
製作にも関わったキートンにしてみれば、社会性もある題材で、これまで演じてこなかったような、葛藤を抱えた役に挑むというのは、やりがいがあったと思われる。
その結果、見た目も話し方も、ファインバーグ本人とそっくりだと評判になったというが、実話の映画化の場合は、こうしたビジュアルイメージの相似は重要な要素の一つとなる。
また、全体の構成に多少の難はあるが、実際のところ、9.11事件後にこうした動きがあったことは知らなかったし、さまざまな立場の被害者や遺族の声を改めて知らしめ、“命の値段”という問題について問い掛けるという意味では、とても意義のある映画だと感じた。
(田中雄二)