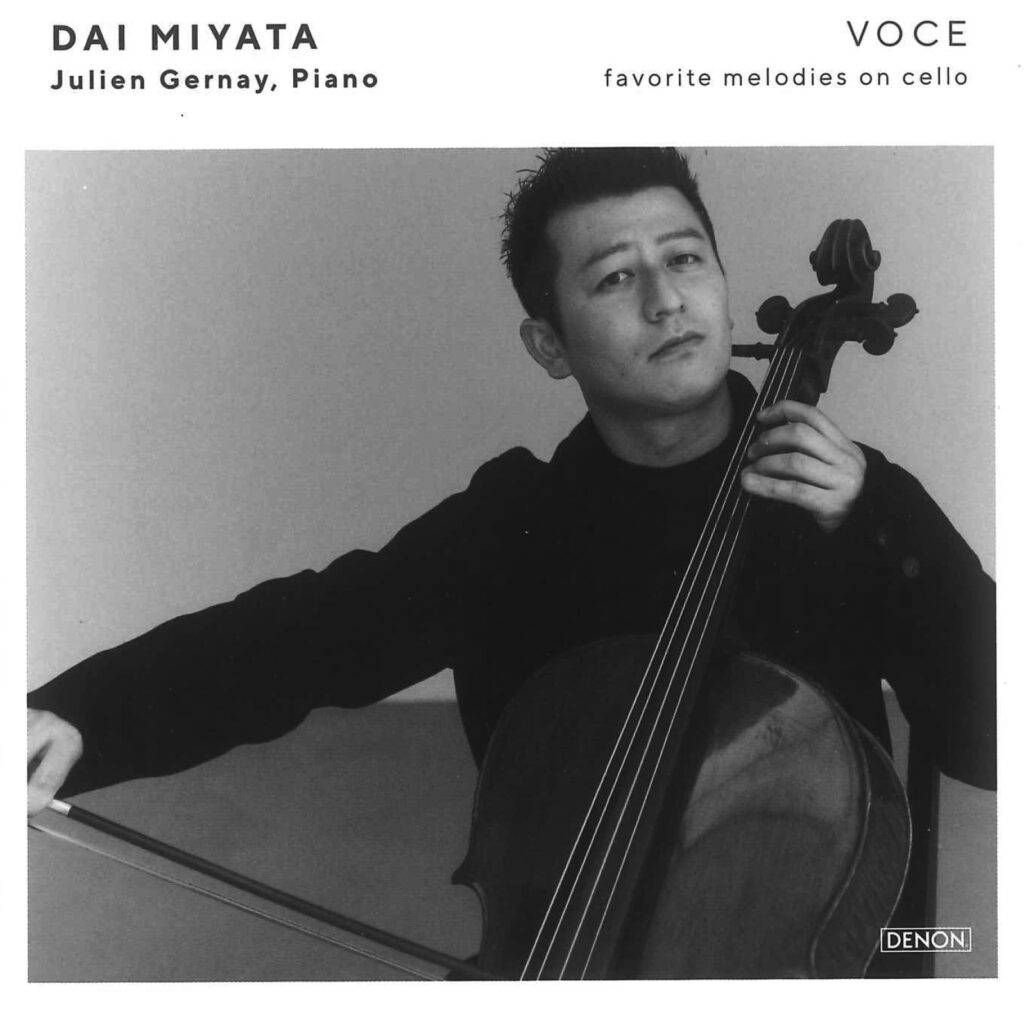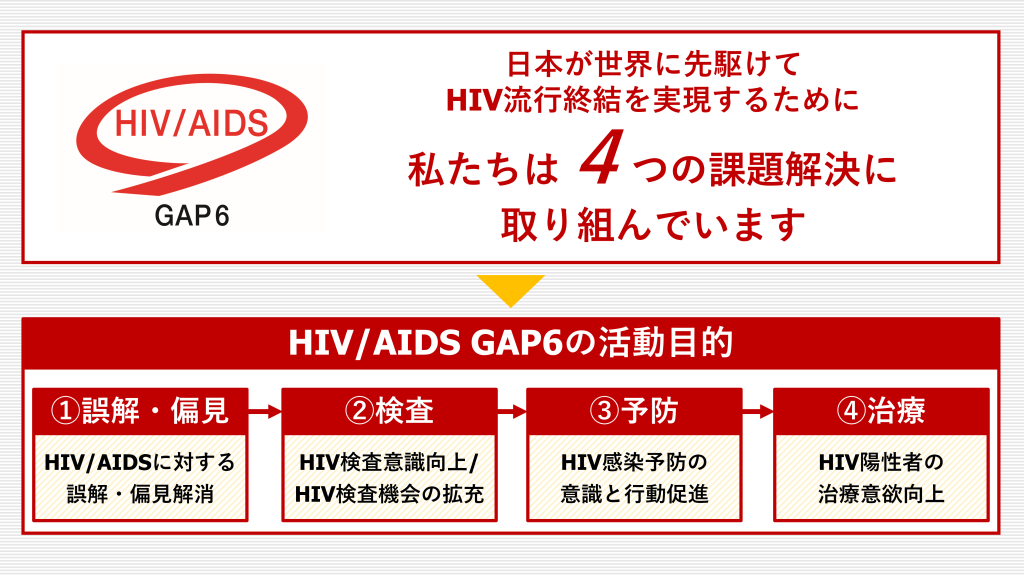民俗的な語法を現代的な手法に転化した20世紀ハンガリーの作曲家バルトーク(1881〜1945)には、スタンダード化している名作も多い。だが、3曲残されたピアノ協奏曲は“無名ではないが、頻繁に演奏されてもいない”といった位置にある。今回ご紹介するのは、その3曲を1枚に収録したディスクである。

バルトーク:ピアノ協奏曲(全3曲)
キングインターナショナル KKC 6745 3300円
ピアノ独奏はピエール=ロラン・エマール。1957年フランス生まれの彼は、現役屈指の名手で特に現代作品の演奏に関しては第一人者といっていい。バックを務めるのはエサ=ペッカ・サロネン指揮のサンフランシスコ交響楽団。58年フィンランド生まれのサロネンも、近現代作品に定評ある敏腕指揮者で、自身優れた作曲家でもある。彼が2020年から音楽監督を務めるサンフランシスコ響は、アメリカの名楽団ならではの機能性を有している。
つまり本盤は、20世紀作品における現代最上位の音楽家による演奏だ。となれば、超モダンでシャープな表現が予想される。ところがここで聴けるのは、明快で表情豊かな、温かみすら感じる音楽である。
バルトークのピアノ協奏曲は、ピアノの打楽器的な扱いが大きな特徴だが、エマールはそれに固執せず、まるで“古典協奏曲”であるかのように表現する。もちろんモダン性や激しさもある、しかしそこに美しさやデリケートな表情が加わっている。サロネン率いるオーケストラも、機能的ながら活力十分。すなわちこれは、無機質なモダニズムの羅列ではなく、極めて“音楽的”な協奏曲集なのだ。
第1番は1926年の作。ピアノの打楽器的用法が際立つ、複雑で革新的な音楽と称されている。だが本盤の演奏は、ソロとバック共に生き生きしていて表情豊かだ。第2番は31年の作。変化に富んだエネルギッシュな作品だが、これまた精彩やデリケートな味わいをたたえた快演が展開されている。同曲はバルトークの最高傑作の一つと評されており、本盤を聴くとその意味がよく分かる。第3番は45年の作。アメリカに亡命して不遇をかこったバルトークは、平明かつ簡素な作風に転じた。生涯の最後に位置するこの曲もしかり。ゆえにここでは、叙情性や民俗色がナチュラルに表現されている。
「これらは、20世紀の孤立した音楽ではなく、バッハ等から続く協奏曲の系譜に位置する楽曲」と、いわんばかりの演奏。こうした“バルトークの古典化”が、現代音楽の最前線に立つアーティストたちによって成されたのは、極めて興味深い。いや、最高位の音楽家だからこそ、この境地に至ったともいえようか。この“身構えずに聴けるバルトーク”、かなり貴重ではある。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 47からの転載】

柴田 克彦(しばた・かつひこ)/音楽ライター、評論家。雑誌、コンサート・プログラム、CDブックレットなどへの寄稿のほか、講演や講座も受け持つ。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)、「1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集」(音楽之友社)。