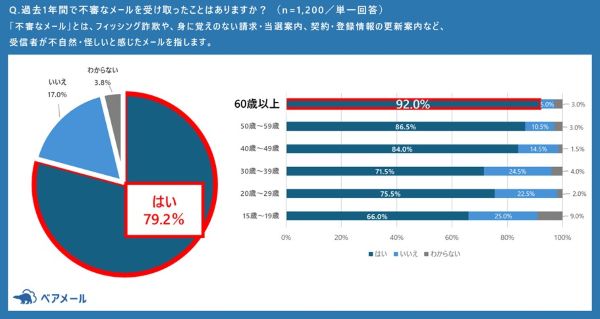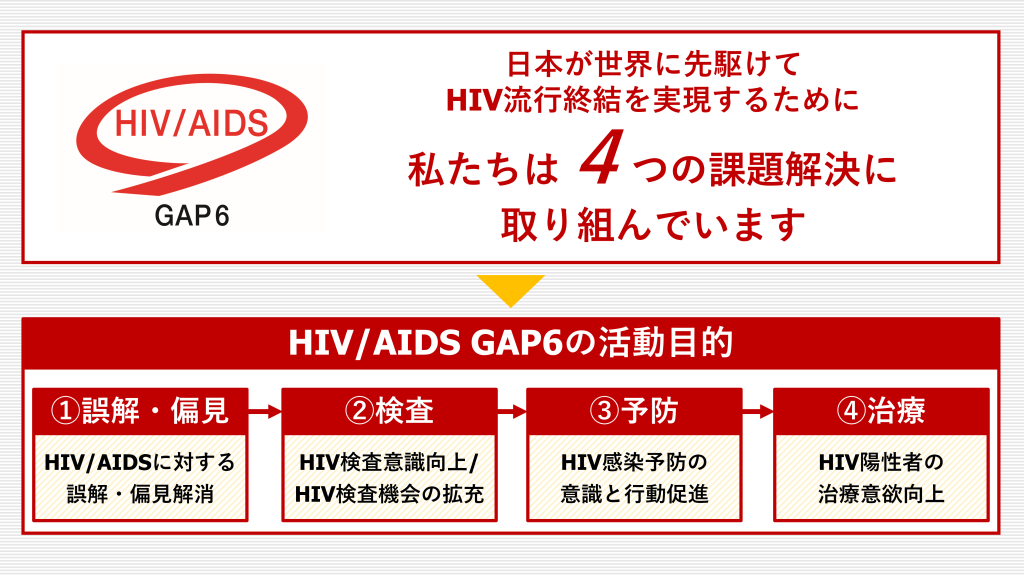『燈火(ネオン)は消えず』(1月12日公開)

古きよき時代のガラス管のネオンを愛し、腕ききのネオン職人だった夫のビル(サイモン・ヤム)を亡くしたメイヒョン(シルビア・チャン)は、SARSが香港を襲った時に、夫にネオンの仕事を廃業させたことを後悔していた。
ある日メイヒョンは、「ビルのネオン工房」と書かれた鍵を見つける。10年前に廃業したはずなのに…と疑問に思い、昔の工房へ行ってみると、そこには夫の弟子を名乗る見知らぬ青年レオ(ヘニック・チャウ)がいた。
メイヒョンはビルの死を伝え、工房を閉めることを告げるが、レオは「師匠にはやり残したネオンがある、それを完成させたい」と力説する。メイヒョンは、夫がやり残したネオンを探し出し、完成させることを決意するが…。
かつて100万ドルの夜景とうたわれ、ネオンサインの看板がきらめく風景が名物だった香港。だが、2010年の建築法等の改正により、20年までに9割のネオンが姿を消したという。
ネオン職人だった亡夫が思い残した最後のネオンを完成させようとする妻の姿を描いたこの映画は、22年・第35回東京国際映画祭「アジアの未来」部門では『消えゆく燈火』のタイトルで上映され、第96回米アカデミー賞国際長編映画賞の対象となる香港代表作品にも選出された。
そんなこの映画は、きらびやかで映像としても映えるネオンを一つの象徴として、失われていくものへの追憶を描いている。その点では、『ニュー・シネマ・パラダイス』(88)などと同種と言ってもいいだろうが、大きく違うのは監督が女性(本作が長編デビュー作のアナスタシア・ツァン)で、主人公も女性であることだ。それ故、男がよく描く(抱く)後ろ向きの追憶とは別種のものになっている。そこが新鮮だった。
ちょっと大竹しのぶと似た感じのチャンが好演を見せる。かつてのネオンきらめく街並みとそれが消えた現在との対比、そしてエンドクレジットに重ねて、実在のネオン職人たちを映したところも感動的。「ネオンは光の書道」というせりふも印象に残った。年を取るとこういう映画は心にしみる。