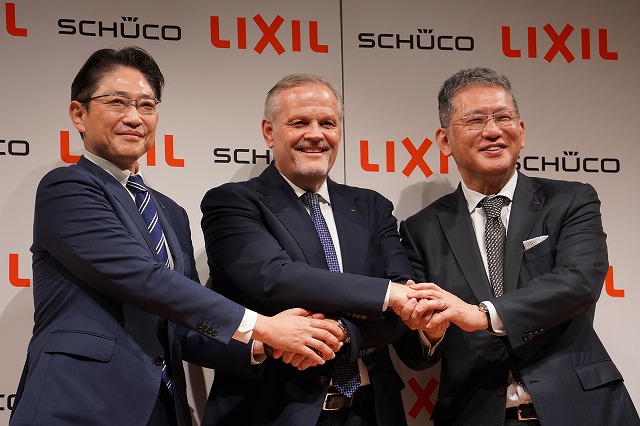予想通りの猛暑と、思わぬ大雨で息苦しい夏だ。だが気分がざらつくのは、それだけではないと分かっている。戦後80年の節目に放映されているNHKの朝ドラ「あんぱん」の幾つかの場面のせいで、意識下に追いやっていたものが芋づる式に引っ張り出されたからだ。
なぜ私は、身近な人々に耳を傾ける勇気がなかったのだろうかー。これである。きっかけは、ヒロインのぶがまっすぐな心で、生徒たちに「愛国心」を教える場面だった。
私の祖母は、女学校の教師をしていた。裕福ではない家庭の出で、努力の末に教師になった祖母も、まっすぐな心で「正しい」こととして軍国主義を教えたとしてもおかしくはない。だが、最愛の長男が戦死した。ベニヤ板の特攻艇「震洋」を積んだ船もろとも、米軍の攻撃でフィリピンと台湾の間のバシー海峡に沈んだのだ。戦死に涙を流してはいけない立場だった祖母は、庭に植えていたコスモスの花をすべて引き抜いたー。私が大人になっておばが教えてくれた。私は祖母に直接、尋ねたことはなかった。
長男、私のおじに当たる彼は、日本軍が決めた「戦死する運命」の理由を探し続けていた。キリスト教徒で「現人神(あらひとがみ)のための死」は受け入れられず、「われ、永遠の中に生きん」と書き残したー。父が教えてくれたことだ。
だが私はもっと突っ込んで聞くべきだった。父がわずかに足を引きずるのはなぜか。ムソルグスキーの「展覧会の絵」が流れると、その場を離れるのはなぜか。戦争がもたらした傷や怒りが理由だと気づいてはいた。
もっといえば、東南アジアの激戦地から生還した親戚や近所の男性たちが抱える傷に耳を傾けようとせず、彼らを「変人」と呼んだりした。傷を誰にも理解されないまま、おじさんたちは鬼籍に入った。
芋づる式に、小学校の平和教育で抱いた疑問も思い出した。「戦争は絶対ダメ」と教師は繰り返したが、そう唱えていれば戦争は起きないのだろうか。テレビでベトナム戦争の映像が流れていた頃で、私には切実な疑問だった。
答えは、記者になって出会った人々から少しずつ得た。2016年に取材したモスクワの「国立グラーグ(強制収容所)歴史博物館」は深く印象に残った。死者1千万人とも言われる、スターリン時代の大粛清と弾圧の歴史、犠牲者たちが残した「生きた証」がマルチメディアを駆使した展示で語られていた。

「沈黙や密告で、市民も独裁体制に加担した。その事実を知り、悲劇はなぜ起きたのかを考える場にしたい」。博物館の目的を説明した34歳のロマノフ館長は、93歳で死去した前館長の知性と鉄の意志を受け継いでいた。モスクワ副市長のペチャトニコフ氏は「どんな民主主義国家でも全体主義者が台頭する危険性がある」と言ったが、今思えば、それは日本や米国への警告だった。博物館は昨年、当局の圧力で休館に追い込まれた。
おじは多数の若者たちとともに、米軍の攻撃で沈む船から海に飛び込んだ。彼らの遺骨は家族には返ってこなかった。この夏の息苦しさを忘れない。懺悔(ざんげ)のためではない。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 33からの転載】

舟越美夏(ふなこし・みか) 1989年上智大学ロシア語学科卒。元共同通信社記者。アジアや旧ソ連、アフリカ、中東などを舞台に、紛争の犠牲者のほか、加害者や傍観者にも焦点を当てた記事を書いている。