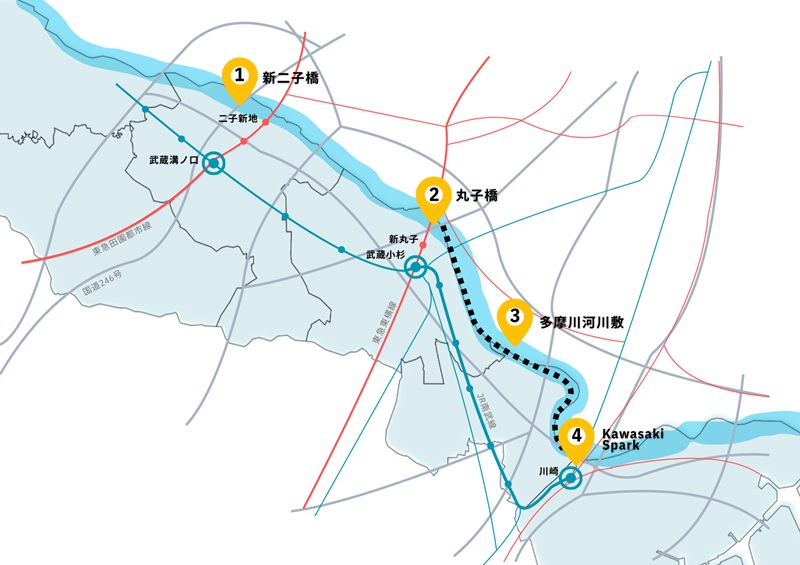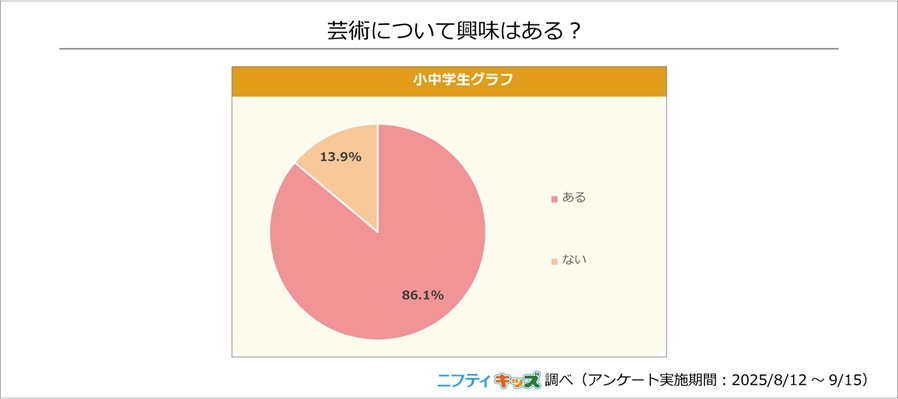旅に目的は必要だろうか。バックパックを背負って世界各国を放浪していた学生時代、漠然とそんな問いについて考えた。明確な目的や計画がなくとも、旅はできると思っていたからだ。むしろその方が発見や驚きが多く、思わぬトラブルからひりひりするような感覚を味わえるのではないだろうか。
ノンフィクション作家・藤原章生氏の『ふらっとアフリカ』(毎日新聞出版)を手に取って、その頃を思い出した。本書は著者が2023年11月からアフリカへ向かい、計7カ月にわたって居候旅を続けた短編集だ。
それは特に目的を持たない「貧乏旅行」だった。シャツ3着と下着、蚊帳とシュラフカバーを詰め込んだリュックを背負い、小さなカメラと盗まれても惜しくないスマホをポケットに忍ばせるだけの軽装。まるでコンビニに立ち寄るような気軽さで「ふらっと」出かけていった。
最初に向かったのはスペイン。そこからジブラルタル海峡を渡ってアフリカ大陸のモロッコへ。バスやバイクタクシーを乗り継いで陸路で南下し、コートジボワールから最終目的地の南アフリカへ飛んだ。

著者は1990年代、毎日新聞の特派員として南アフリカのヨハネスブルクに赴任していた。クーデターが起きれば他国へ飛び、内戦の取材にも明け暮れ、締め切りに追われる中で、大陸の森羅万象を掴(つか)み取ろうと常に前のめりだった。以来、アフリカを訪れたのは23年ぶり。今回は、受け身の姿勢に徹したことで肩の力がすっと抜けた。積極的に人々に話し掛けるのではなく、相手の口から自然に出てくる言葉を待った。その何げない日常のやり取りからは「アフリカ=貧困」という先入観に縛られない、等身大の人々の姿が立ち上がってくる。
それにしても、いくらアフリカで特派員経験があるとはいえ、60歳を超えた著者が、出会って間もない人の家に「居候」とは随分、思い切った行動だ。逆に年を重ね、さまざまなしがらみから解放された今だからなせる技なのかもしれない。その旅路は、決して順調ではなかった。
西サハラでは、ロバのいる居候先で3日目に「パンを食べたら出ていけ」と家を追い出され、灼熱(しゃくねつ)の砂漠でヒッチハイクをする羽目に。シエラレオネでは警官を装った大男からしつこく賄賂を要求された。
かといえば人々の眩(まぶ)しい笑顔や忘れがたい光景にも出くわした。ガンビアの乗り合いバスでは、2人のシスターによる聖書の朗読が美しく、思わずスマホを取り出した。受け身でいられなくなった瞬間だ。3日間を過ごした海辺の村では、別れ際に族長の妻が涙を流してくれた。南アフリカでは特派員時代の助手に再会し、生活の激変ぶりに驚かされた。
出会いと別れを繰り返し、著者はますます、アフリカの魅力に取り憑(つ)かれていく。そして現地語の習得にも励み、この9月半ば、再び日本をたった。今ごろ南アフリカの友人たちに囲まれ、現地にどっぷり漬かっているはずだ。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 39からの転載】

みずたに・たけひで ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、「日本を捨てた男たち」で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。10年超のフィリピン滞在歴をもとに「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材。