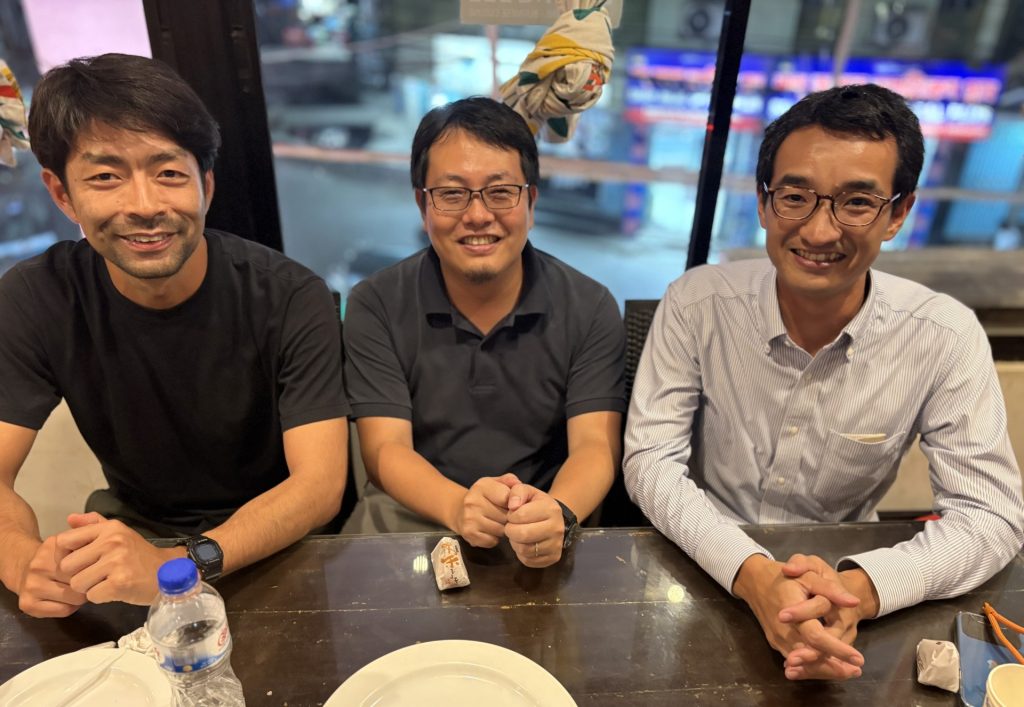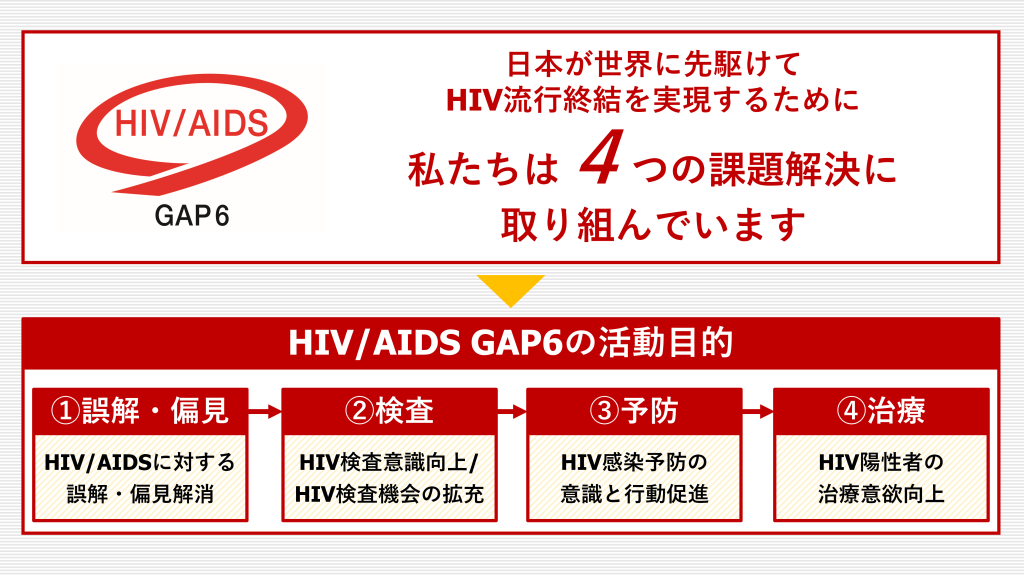NHKで好評放送中の連続テレビ小説「虎に翼」。女性として日本で初めて法曹界に飛び込んだ主人公・佐田寅子(伊藤沙莉)の物語は、まもなくクライマックスを迎える。「女性の社会進出」や「女性の生きづらさ」を描いた物語は、数十年前の戦前から戦後の昭和を舞台にしながらも、私たちが生きる現代にも重なり、大きな反響を呼んだ。全話の脚本執筆を終えた吉田恵里香氏が、作品に込めた思いを語ってくれた。
-「虎に翼」の脚本執筆を終えた今のお気持ちは?
とても恵まれた現場で、楽しく執筆することができました。今はやりきって非常に満足していますが、後半の執筆に入った頃から、「終わらないでほしい」という気持ちが湧いてきました。登場人物をさらに掘り下げたり、女子部時代のエピソードを盛り込んだり、やりたいことがたくさんあったので、あと3カ月くらいあれば…と思って。ただ、それも「虎に翼」らしいのかなと。
-寅子役の伊藤沙莉さんの印象はいかがでしたか。
寅子役には伊藤さんを希望していたので、決まった時はとてもうれしかったです。伊藤さんのお芝居が素晴らしく、寅子の喜怒哀楽を表情豊かに表現してくださったので、「伊藤さんなら、ここを嫌われないように演じてくれるはず」と期待して書いたシーンもあります。後半に入った最近の演技も、とてもすてきです。18歳の寅子から演じてきて、中年になっても口調は若々しさを残す一方で、所作やまなざし、ほほ笑みなどで年齢を演じ分けていらっしゃるのが、本当に素晴らしくて。
-寅子の口癖である「はて?」というせりふは、どのようにして生まれたのでしょうか。
寅子の疑問やおかしいと思ったことを、わかりやすく提示できる言葉が欲しかったんです。ただ、寅子は誰かを否定や攻撃したいわけではないので、あまり強くない言葉にしたいと。例えば、「どういう意味ですか?」、「違うんじゃないんですか?」、「はあ?」などの言葉だと、対話が終わってしまいます。この作品では「対話する」、「思ったことを口に出す」がテーマだったので、その導入になるような言葉を…と考えた結果、思いついたのが「はて?」でした。

-寅子だけでなく、明律大学女子部の同級生たちや親友で兄嫁の猪爪花江(森田望智)まで、幅広い女性たちの生き方を描いていることも本作の特徴ですが、その際に心掛けたことは?
「虎に翼」では、「人権」や「自分の人生を自分で選択する」が大きなテーマでした。ただ、寅子だけではそれを描ききれないので、女子部の仲間を最後まで登場させることは最初から決めていました。といっても、私自身が働いている分、どうしても働いている側の視点に立ってしまい、視野が狭くなりがちです。でも、バリバリ働きたい人やほどほどでいいと思っている人、あるいは家庭を守りたい人など、世の中にはさまざまな考えの人がいます。みんなが自分の望む場所に立てることが最も大切と考え、専業主婦の花江も含め、公平になるように、それぞれの配分には気を付けました。最終的に、役者の方々や演出の皆さんの力によって、それぞれのキャラクターが視聴者の皆さんから愛される存在になったことは、大変うれしく思います。
-その中で、第1回から寅子と共に歩んできた花江に託した思いをお聞かせください。
花江は、社会に出て働くより、家庭を守ることに幸せを感じる人で、もう1人の主人公のつもりで描いていました。現代も、社会に出てバリバリ働く人がいる裏で、それを支えるために誰かが生活のケアをしなければいけない社会構造があります。言ってみれば、二人三脚のはずなのに、なんとなく支える側が世間から“二軍扱い”されてしまう。そこに大きな違和感がありました。家庭を円満に保ち、黙っていても食事が出て、清潔な家で暮らす心地よさは、その人の努力なしにはありえません。それが、どれほど大変なことか知ってほしいと思い、花江はその道のプロのつもりで描きました。
-なるほど。
とはいえ、家事をすべて1人で担うのではなく、家庭はみんなで支え合うべきと考え、猪爪家は途中からそういう方向に変わっていきました。ただし、その主戦力は、あくまでも花江です。だから、同居する嫁・姑問題をはじめ、彼女のいろいろな考えも見えてくるようにしました。仮に、花江視点の“「虎に翼」 side 花江”版があったとしても、きちんと成立するようにしたつもりです。
-一方、女性の生き方を軸にした物語の中で、男性を描くにあたって意識したことは?
「女性の社会進出」や「女性の生きづらさ」を描いた作品ではありますが、それは社会に生きるすべての人の生きづらさにつながると思っています。“男性の特権”のようなものもあるとは思いますが、逆にそれゆえ生きづらさを感じたり、しんどい思いをしたりする男性もいるはずです。また、女性が生きやすくなることで、男性が生きにくくなるのもおかしな話で、全ての人が生きやすいのが、本来あるべき社会の姿ではないでしょうか。だから、その点は気を付けて描いたつもりです。
-一見、女性の社会進出に理解あるようでいて、最終的に寅子を傷つけてしまった恩師の穂高教授(小林薫)のような人もいましたが。
男女を問わず、全てに関して善人でいられる人はいないと思っています。理解あるように見えて傷つけてしまう人もいれば、全く理解できない人もいる、というように、キャラクターのグラデーションは意識しました。私自身にもある意味、穂高先生的な部分はあると思っていますし、「これだけ寄り添ってあげているのに」という押しつけがましい気持ちが少なからず生まれてしまうのが人間です。寅子だって常に正しいわけではなく、間違えることもあります。問題は、そこといかに向き合っていくか、です。だから、変に美化することなく、誰だって間違えるし、誰にでも駄目なところがあるというのは、すべての登場人物について心掛けていました。
(取材・文/井上健一)