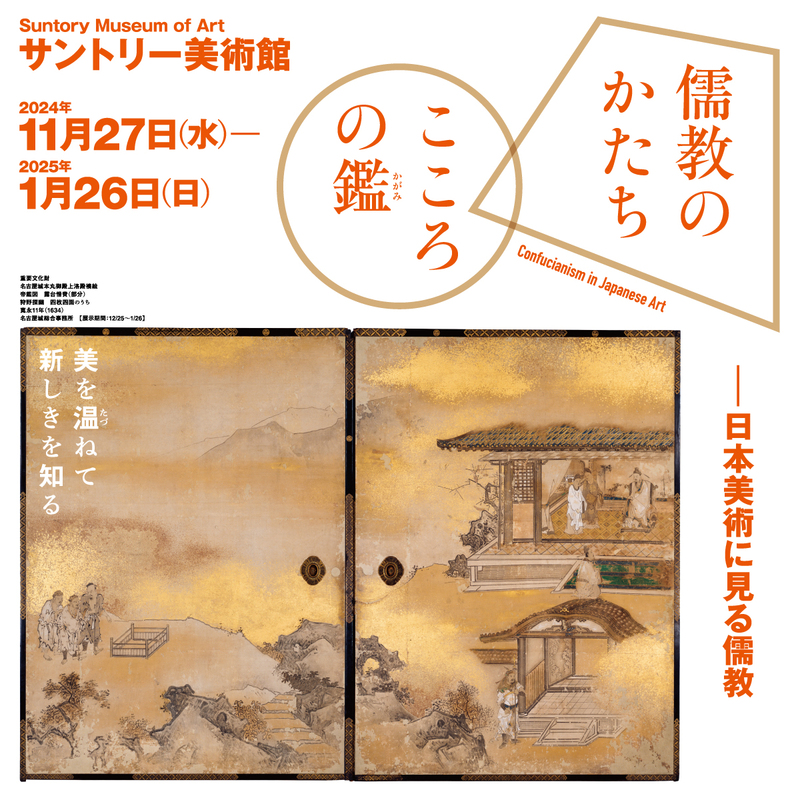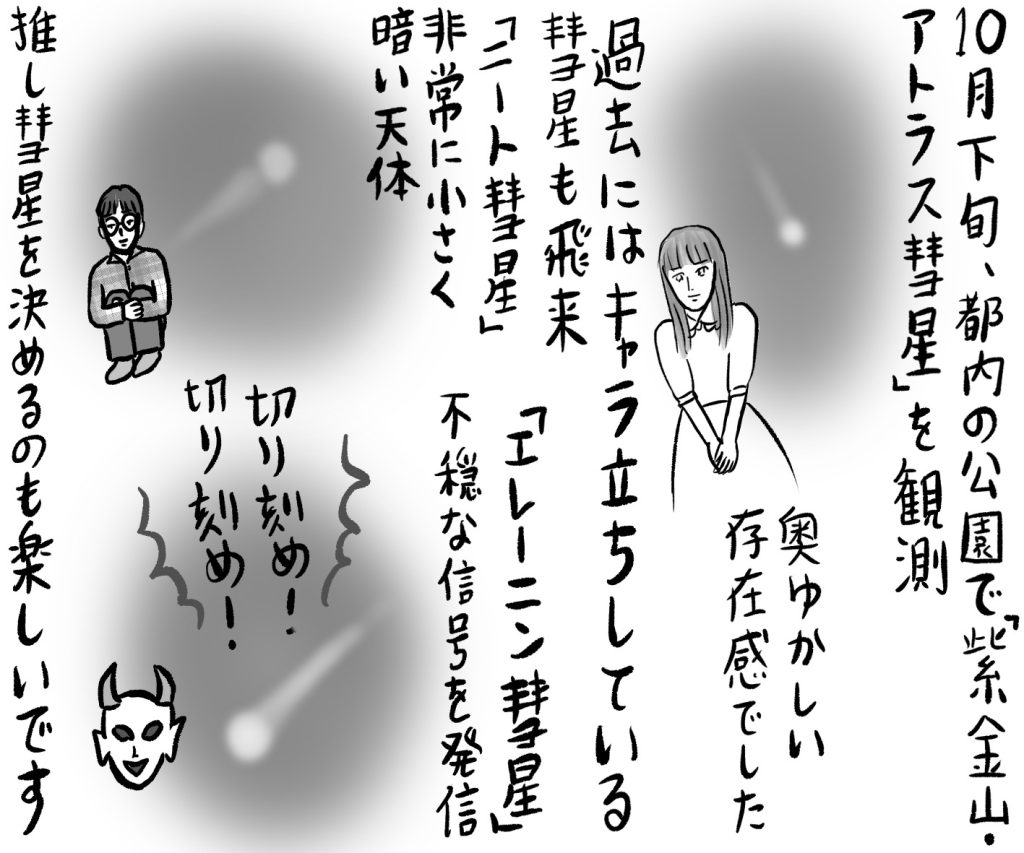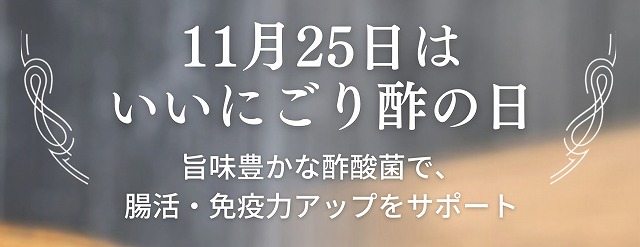12月18日、この1年、私たちを魅了してきたNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が完結した。事前の番宣などで脚本の三谷幸喜が「今までにない主人公の最期」と語っていたので、大団円は期待せず、ある程度の心構えはあった。
それでも、全く予想しなかった主人公・北条義時(小栗旬)の最期は衝撃的で、きちんと受け止めるまで、少々時間がかかったほどだ。

筆者はこの作品をこれまで、「過酷な時代を生きる人々の生きざまの物語」と解釈してきた。実は放送開始前、「御家人たちの権力闘争を描く」と聞いたときは正直、コロナ禍を始めとする数々の困難に直面するこのご時世、日曜夜8時に血生臭い権力闘争を見せられたらきついのでは…とやや不安を感じていた。
だが、ふたを開けてみれば、そこで繰り広げられたのは、過酷な時代と非情な運命に翻弄(ほんろう)されながらも、懸命に生き抜こうとする人々の物語。それは、今を生きる自分自身にも重なり、日々の困難を乗り越える原動力となった。
上総広常、木曽義仲、源義経、梶原景時、比企能員、源頼家、畠山重忠、和田義盛、源実朝…。非業の死を遂げた人物を数えればきりがないが、明日に向かって懸命に生きようとする彼らの姿は鮮烈で、その生きざまが美しく気高かったからこそ、壮絶な最期が際立ったとも言える。
では、そのちょう尾を飾り、最終回で最期を迎えた主人公・義時の生きざまはどんなものだったのだろうか。
もともと、伊豆の田舎の小さな豪族の次男坊で、権力と無縁に育った気のいい穏やかな少年・義時は、源頼朝(大泉洋)と出会ったことで壮絶な権力争いに巻き込まれる。
頼朝の下で源氏のライバル、平家を滅ぼし、鎌倉に幕府を開くと、主君・頼朝亡き後はその遺志を継ぎ、鎌倉を京と並ぶ武家の都へと発展させていく。
だが、その思いを真っすぐに貫こうとした義時は、本心とは裏腹に、共に戦ってきた仲間を討ち取り、身内や主君すらも死に追いやる非情で苦しい決断を繰り返し迫られる。それが、義時を次第に恐るべき権力者へと変えていくことになった。
とはいえ、その間、義時の胸にあったのは私利私欲ではなく、亡き兄・宗時(片岡愛之助)や頼朝の思いを受け継いだ「鎌倉のため、坂東武者のため」という思いただ一つであることは、1年間ドラマを見守ってきた視聴者の誰もが認めるところだろう。
それは、最終的に、鎌倉を守るため、自分の命すらも投げ出そうとする第47回の決断に結びついた。そんな義時の生きざまを表現するのに最もふさわしい言葉は「実直さ」ではないだろうか。
非情な決断を繰り返すことで闇に染まっていったのも、元をたどればその実直さ故。最終回に登場した運慶(相島一之)が義時に似せて作った醜い仏像は、憎悪と憎しみと悪意、時代が生んだあらゆる負の感情を抱え込んだ権力者・義時を象徴している。
だが、そういった負の感情から逃げることなくスポンジのように吸収していったこと自体、「義時が実直だったから」ではないだろうか。
最終回、三浦義村(山本耕史)が、義時に対する積年の嫉妬を爆発させる中で、「おまえにできたことが俺にできないわけがない」と断言していたが、利で動く義村には決してできない行為だろう。