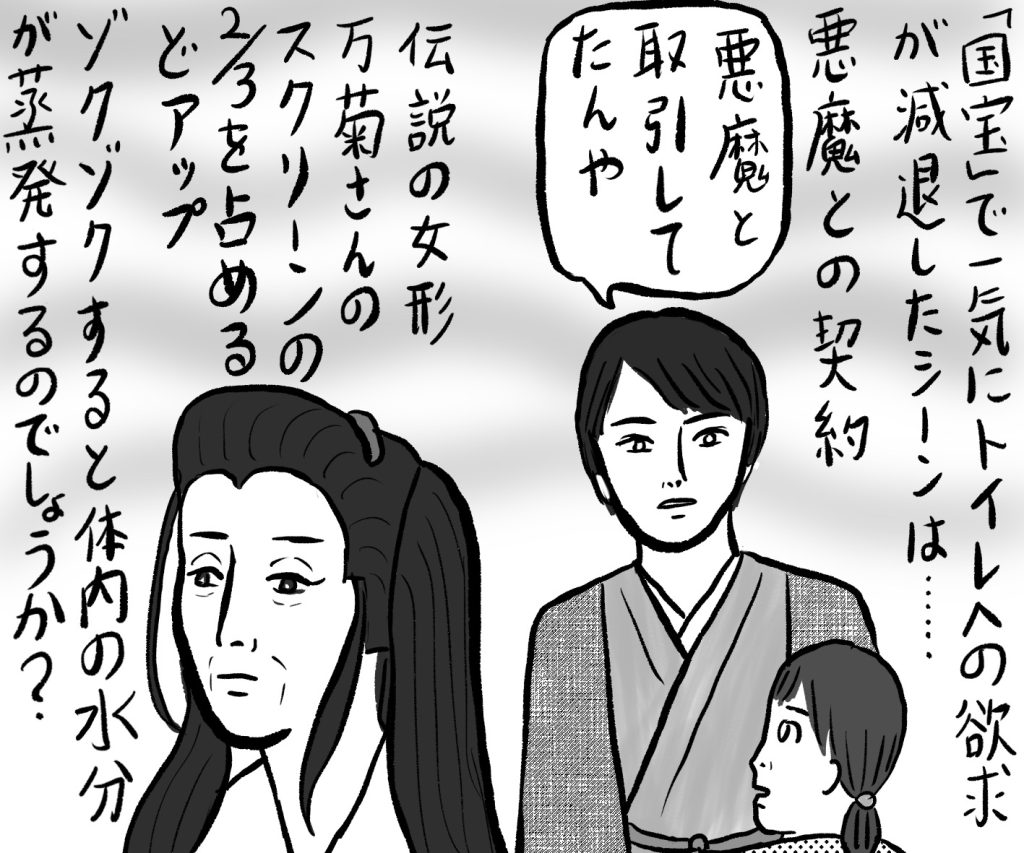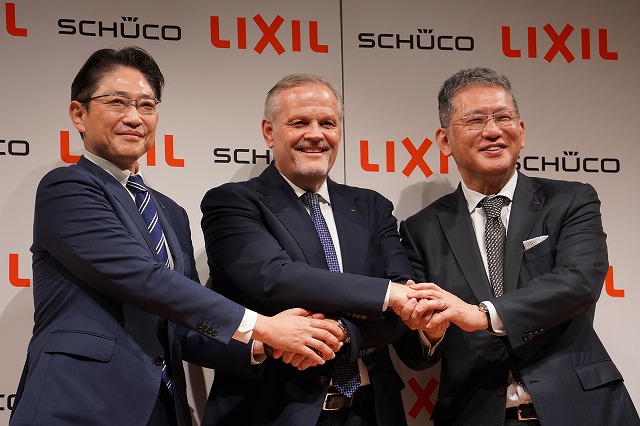昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されたキリル・セレブレンニコフ監督の『リモノフ(Limonov The Ballad)』(2024)が、日本でも今年9月初旬から封切られているが、いろいろな意味でたいへん話題性のある映画だ(ロシア語では2番目の音節にアクセントがあるので、「リモーノフ」と表記するのが望ましいのだが)。
まず、主人公のモデルとなっているのが、エドワルド・リモノフ(1943ー2020)という破天荒で露悪的な実在の作家・政治活動家であること。ソ連時代のハリキウ(現ウクライナ)に生まれ、〝不良〟となり、アンダーグラウンド詩人として知られたが、1974年アメリカに亡命し、ニューヨークでのスキャンダラスな私生活を自伝的小説『ぼくはエージチカ』(1979)に描いて脚光を浴びた。パリへの移住を経て、1991年ソ連に帰国。その後、セルビアの義勇兵になり、極右民族主義であり極左でもあるような「国家ボリシェヴィキ党」を結成。社会に不満をもつ若者たちの支持を受けカリスマ的な政治指導者となるも、その過激な言動により何度も拘束される…。
こうした波乱万丈の生涯を小説『リモノフ』にしたのが、フランスの人気作家エマニュエル・キャレール(カレール、1957年生まれ)である(邦訳は、土屋良二訳、中央公論社、2016)。ちなみに、彼の母エレーヌ・カレール・ダンコースは世界的に著名なロシア史研究者だ。キャレールはリモノフに密着取材するとともに、『ぼくはエージチカ』をはじめとする彼の作品を参考にこの「伝記小説」にまとめた。あらゆる〝常識〟を無視し、矛盾に満ち満ちたリモノフの強烈な個性が、キャレールを虜(とりこ)にしたことはまちがいない。
そして、キャレールのこの小説を原作として映画を撮ったのが鬼才セレブレンニコフ(1969年生まれ)なのである。現代ロシアを代表する演出家・監督として、数多くの国際的な賞を受賞。映画では『チャイコフスキーの妻』や『インフル病みのペトロフ家』、『レト』などの秀作を次々に発表してきた。
もちろん、ロシアの〝外側〟からリモノフを観察したキャレールと、〝内側〟の人間としてロシアの激変を経験したセレブレンニコフでは、リモノフ像の描き方が異なるのは当然だ。あるインタビューでセレブレンニコフは、副題を「バラード(物語詩)」としたのは、伝記的事実にかなり自らの虚構を加えたためだと述べている。また、仮面をかぶった派手なパフォーマンスと、ルサンチマン(恨み)を抱えた傷つきやすい詩人気質の内面という観点から、この作品を「ロシアのジョーカー」と呼ぶこともできるという。
彼は、もともとプーチン政権から迫害を受けながら活動を続けていたが、『リモノフ』の撮影を途中までロシアで進めていた2022年2月ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めたため、その後亡命して国外で作品を完成させた。現在、ロシアは「帝国の復活」や「西側との永久戦争」を目指す恐ろしく狂った「リモノフ的世界」に変貌してしまったため、図らずも映画『リモノフ』は鋭い今日性を持つことになった、というのが監督の自己評価である。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 35からの転載】

沼野恭子(ぬまの・きょうこ) 1957年東京都生まれ。東京外国語大学名誉教授、ロシア文学研究者、翻訳家。著書に「ロシア万華鏡」「ロシア文学の食卓」など。