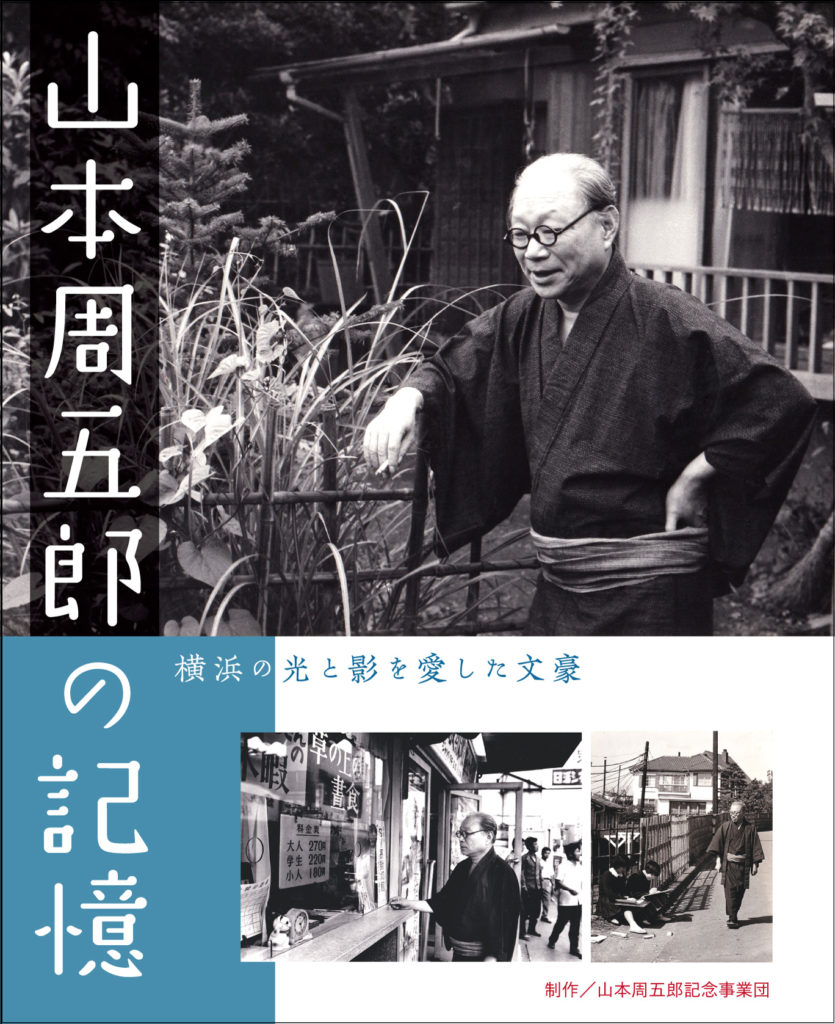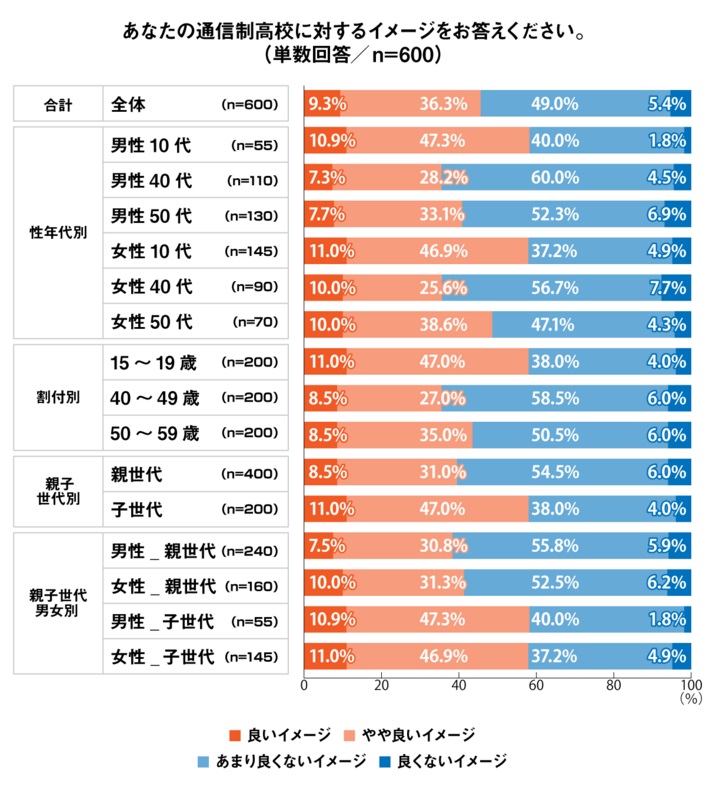『赤ひげ診療譚(しんりょうたん)』『青べか物語』『樅ノ木(もみのき)は残った』『さぶ』。これらは昭和を代表する、作家・山本周五郎の小説群である。山本周五郎記念事業団は、『山本周五郎の記憶 横浜の光と影を愛した文豪』(発行:歴史探訪社、発売元:メディアパル、2400円=税別)をこのほど発売した。
今回の発刊の狙いについては「横浜で人生の佳境を過ごした周五郎の足跡を辿(たど)り、周五郎が何を考え何を生み出したかを捜す旅、それは、なぜ今なお周五郎作品が日本人に広く愛されているかという疑問への答になるはずである」(犬懸坂祇園氏によるあとがき)と指摘している。
本書の巻末にある略年譜をめくってみると、いずれも山本周五郎が51歳から60歳の時に世に出していることに驚く。周五郎は1967年に63歳で没しているので、晩年の10年と少しの間に先ほどの数々の作品を世に出しているのだ。
■人生の三分の一
筆者も60歳を越え、周五郎の没した年齢に近いので、周五郎がどのように生きてきたのかに興味を持ち、略年譜にさらに目を通してみた。
1903(明治36)年生まれの周五郎は、大正期に10代を過ごしているので、永井荷風、谷崎潤一郎、志賀直哉、武者小路実篤、芥川龍之介、菊池寛などの作品を読んだかもしれない。
20代は大正末期から昭和一桁の時期だ。ちょうどこの頃、新聞に小説が連載されるようになり、大佛次郎や吉川英治が大人気になる。大衆文学の誕生の時期であり、文学史的には周五郎もこの系譜に連なるだろう。1926(大正15・昭和元)年には、『須磨寺附近』が『文藝春秋』に掲載され、自身も作品を発表し始めている。
20代末から40代初めの15年間は、結婚、父親や最初の妻との死別など、さまざまな経験をしている。戦前から戦後にかけてのこの時期は、「戦争」が文豪の心に影響を与えたことも容易に想像できる。
周五郎は昭和21(1946)年、新しい家族を迎え横浜の本牧(横浜市中区本牧元町)に居を構えた。63歳で亡くなるまで、人生の三分の一を本牧で過ごし、ここで数々の名作を世に送り出すことになった。
■観客を観察
本書には、本牧での周五郎の様子が写真や関係者の証言でつづられていて、周五郎が本牧を愛し、そして本牧の人々も周五郎を愛していたのがよくわかる。
決まったルートを散歩し、決まった食堂で昼食をとり、その後、映画を観る。1日の締めに酒を飲む。本牧での生活はこんな具合だった。
毎日の映画鑑賞について、こんな周五郎の言葉が引用されている。「映画そのものより、周囲の観客を(気づかれないように)観察し、会話を聴くのが目的だといってもよいだろう。この習慣は気分転換にもなるし、仕事の材料も得られるから、晴雨にかかわらず毎日やっている」と。周五郎の作品が多くの人に受け入れられたのは、それが人々自身の物語だったからもしれない。
この一言に目が留まったのは、筆者が、同じことをある女性歌手が言っていたのを思い出したためだ。
「私はファミレスなどに行くと、他のお客さんの話に聞き耳を立てるんです。いろいろなドラマもあるし、詩作の参考になることもあります」と。こんなことを言っていたと思う。この歌手がファミレスに行くのに少し驚いたが、周五郎同様、半世紀近くにわたって人々の心に残る歌を出し続けている。そう、松任谷由実さんだ。
本書では「(前略)、『英雄、豪傑、権力者の類にはまったく関心がない』と本人(=周五郎)も語っているように、壮大な作品群の背骨をなしているものは、名もなき市井の人々の生き様だ。殊に貧困や病苦や絶望の淵にありながらも、ひたむきに生きる凜とした人間の美しさにある」(黒川昭良氏、27ページ)と、周五郎作品の魅力を解き明かしている。
映画館で他の観客たちの話を聴くのも、市井の人々の多くの「声なき声」を周五郎なりに収集し、それらを作品の中に昇華させたのかもしれない。しかも、彼の作品に対する評価であった「直木賞」をはじめ「毎日出版文化賞」「文藝春秋読者賞」などをことごとく辞退している。そこからは、彼が「権威」を嫌い、つねに庶民の心を保とうとしていたことを示唆している。
文学作品はどんなに流行したものでも、時間の経過とともに忘れ去られてしまう。しかし、作品だけではなく、その作者がどんな人間だったか、その記憶や記録が作品と結びつくことによって、作品に光が当たり続けるのではないだろうか。「赤ひげ診療譚」ではなく、「山本周五郎の『赤ひげ診療譚』」だ。
周五郎の作品はいずれも60年以上前のものである。本書で文豪の人となりを知り、再度作品を読み直すのも良いだろう。