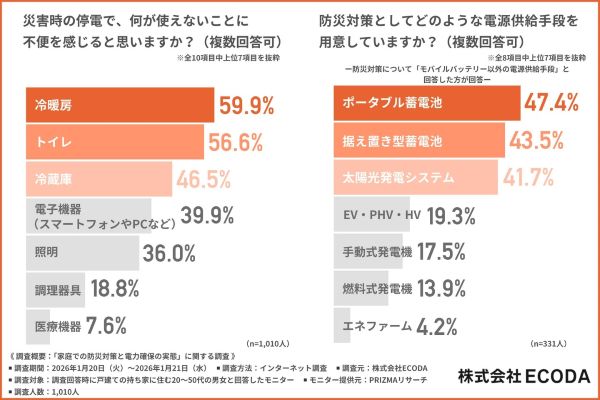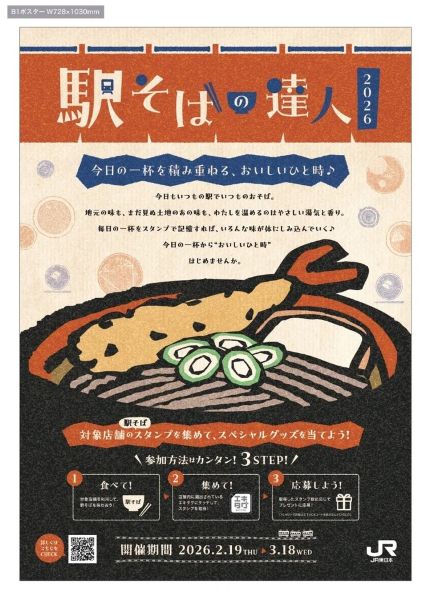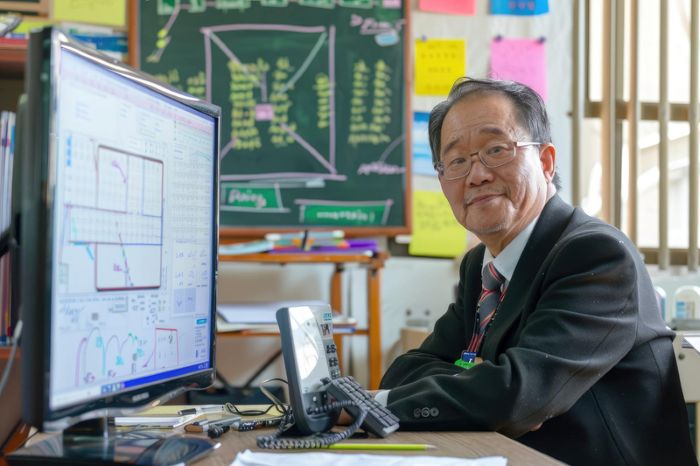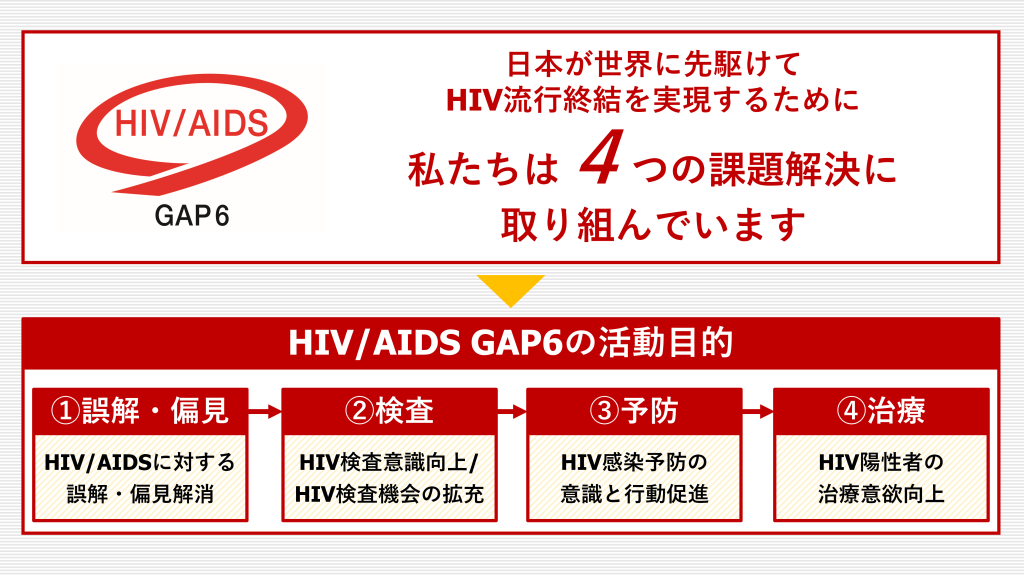上昇志向の強い日本人商社マンが、出張先のアメリカ北西部・モンタナ州の牧場でカウボーイの文化に触れて人生を見つめ直す姿を描いた『東京カウボーイ』が、6月7日からYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次公開される。主人公のヒデキを演じた井浦新、ヒデキの上司で恋人でもあるケイコを演じ、共同脚本も担当した藤谷文子、そしてマーク・マリオット監督に話を聞いた。

-まず、映画化の経緯を。監督の実体験を基にしたと聞きましたが。
マリオット もう30年以上前になりますが、日本に2年間住んでいました。それは本当に大事な経験、学びの時間でした。静かに傾聴するということを学んだ時期でした。山田洋次監督の見習いとして『男はつらいよ 寅次郎心の旅路』(89)に参加するという機会も得ました。その後、ある雑誌の中で「日本の会社がアメリカで牧場を所有して、牧場の経営やカウボーイのあり方を日本人の社員が学んでいる」という記事を読みました。その時に「これはすごい。これはまさに映画だ」と思ったのが発端です。そこから実現するまでには何年もたっているのですが、私はテレビやビデオの分野で長い経験がありましたので、初めて長編劇映画を撮る題材として、これは自分でもつながりを感じると思って、友人でもある本作のプロデューサーのブリガム・テイラーに、アイデアをピッチしたんです。そうしたら彼が関心を持ってくれて、そこから2人でストーリーやキャラクターがどのように変化していくのかを考えて、「日本のカウボーイ」というコンセプトが始まりました。
-カウボーイの文化についてはどう思いましたか。
井浦 日本で暮らしているとカウボーイの文化に触れることはないですし、日本の牧場とも全然違いますから、彼らがどういう暮らしをしているのかに興味がありました。撮影現場にも出演しているカウボーイたちが何人かいましたが、実際に自然や生き物たちと共に暮らしている彼らがどんな人たちなのかなと。初めて本物のカウボーイを目の当たりにして、カルチャーショックというよりも、学ぶことが多いと思いました。
藤谷 今回の自分の役割を、全く違った文化やプランを持った人たちを会わせた場合、どこに人間同士としてのつながりを見つけることができるのかを探すことだと思っていました。その中で、モンタナに行ったことは何度かあったので、モンタナの広大さや日本との違いは、自分でも感じたことがありました。それでモンタナでも温泉が出ていることは知っていたので「これだ!」と思いました。どうしたら人種の違う人と人とがつながれるのかというテーマの中で楽しくやらせていただきました。結局、共同脚本のデイヴ・ボイルも私も、違う国に住んだ経験があるので、何を大事にしたらいいのかというのは多分自然に出てきたのだと思います。
マリオット 違いよりもむしろ共通点の方が多いわけです。ただ、今私たちの住んでいる世の中は、本来なら似ている点が多いのに、分断の要因が多いですね。今回は、特定の文化に着目して描いていますが、例えばモンタナにやって来た人も、そこにいればやっぱり地元の人と似てくるということ。共通点を見つけ出せると思うんです。それが本作が描いた美点だと思います。私が若い時に日本に住んでいた時も、違いよりもより多くの共通点を見いだすことができました。
-最初に脚本を読んだ時にどう思いましたか。また実際に演じてみてどう感じましたか。
井浦 まず、好きな脚本だなと思いました。温かさを感じましたし、ある意味ヒデキの再生の物語でもあります。ヒデキを通して、人はどんな状況でも変化していくことができる、希望の物語でもあると思いました。とても普遍的で、自分の中にある身近なものにも寄り添える作品だと感じました。だからこそ、自分がヒデキを演じることで、その思いをどうパフォーマンスしていけるかという点でも、これはすごいチャレンジになると思いました。たくさんの人たちが共感できる題材だからこそ、それに対してどういうアプローチをするかで、見え方や伝わり方は変わっていきますから、僕自身が試されるなとも思いました。