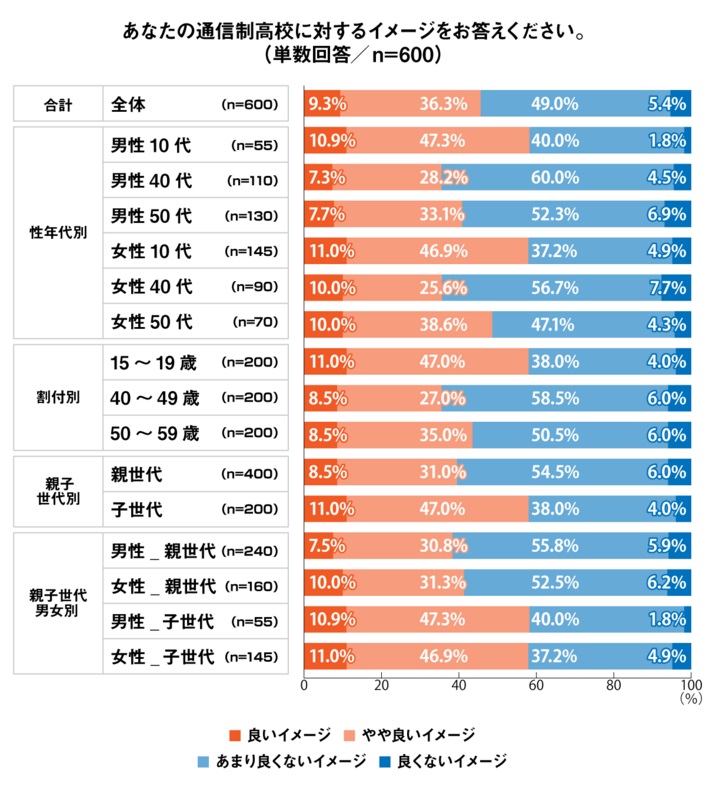太平洋の大海原を望む高知県。背後には豊かな山と川が広がる。その魅力を、そこにいる“人”を通じてじっくり伝える連載インタビュー。第4弾は高知県内にIターン・Uターン移住し暮らしている人たちに「高知」について聞いた。
■だから私は高知に移住した
大阪府出身の市吉秀一さんは、サーフィンが好きでよく高知に通っていた。大阪市内の出版社に勤務。食系雑誌の特集で、高知の地元農家と知り合った経験がきっかけとなり、2013年に高知市に移住した。「高知って食べる物がおいしいし、人が面白い。あちこちに呼ばれて、一気に知り合いができた。大阪にいるより楽しいかも、みたいな(笑)」
意気投合したのは、高知県いの町出身の刈谷農園の刈谷真幸さんだ。日本一の清流ともいわれる仁淀川をたたえるいの町は、「ショウガ栽培の発祥の地」でもある。「僕の先祖が104年ぐらい前からこの山の上で栽培を始めて、ここからタネが平場に下りていき、県下全域が産地になった」

17年ほど京都で料理関係の仕事に就いていた竹内太郎さん。四国山地の山間部、仁淀川の上流域にある仁淀川町に引っ越してきたのは2014年のことだ。「何か自分なりのモノ作りがしたいなと思った時に、昔ながらの暮らしが残っているところで、暮らしながらモノを作っていくことに真実味があるんじゃないかなと思って。それで引っ越して、こちらで仕事を始めました」。元々「仁淀川の下流で高校生まで泳いでいた。遡上(そじょう)してきた感じ」というUターン移住者だ。

カツオ漁で知られる土佐湾に面した中土佐町で小さな有機農園を営むのは、中里さん夫婦。妻の早紀子さんは兵庫県出身。就職を機に上京して東京で10数年働き、2018年に移住してきた。「結構忙しくて、10年後の自分を考えた時に、このままのペースで働けるのかなと」。日本国中を旅行した際に高知が気に入り、移住を検討し始めたのが2015年頃だという。移住後に知り合って結婚した夫の拓也さんの地元は神奈川県。「アメリカで20年ほど生物の研究をしていました。高知は、幼少時代からおばあちゃんの家に遊びに来たりしていて、いつかこんなところで田舎暮らしをしたいなと思ってて」。2013年、帰国して高知に定住を決めた。

■暮らすようにモノを作る、山間での暮らしと仕事
移住時には何を作るかをまだ決めていなかったという竹内さん。「お腹が痛いとドクダミを乾かして飲み、擦り傷をしたらヨモギを塗り込む」。家の周囲の自然がそのまま薬箱だった時代の暮らしが、仁淀川町の山間部では続いているという。「植物と一緒の暮らしぶりが、まだかろうじて受け継がれていました。暮らしの中のモノ作りは、自分たち、もしくは親戚用のロット。手作りで十分まかなえる量なので、とても手を掛けられていて味わいも豊か」
仁淀川町の山間地で盛んなのは茶葉の栽培だ。植物と共にある暮らしを自分のフィルターを通すことで新しい提案につなげようと、「山に自生している山野草を味わいのベース」にしたブレンドティー作りを始めた。山間の元保育園や廃校になった小学校の建物を借りて作るお茶は、今では素材が80種類、レシピが100以上に及ぶという。
オーダーメードの注文は思わぬところからも。5年ほど前に、高知県立牧野植物園から注文が来た。「牧野富太郎由来の植物を使ってブレンドティーを作れないか」。最初に作ったのは富太郎が亡き妻の名前を付けた新種のササ、スエコザサのお茶。「博士が唯一、親族の名前を命名した植物。植物園でもスエコザサはスター。スエコザサを使ってお茶にすることに、緊張感がとてもありました」。ペパーミントをブレンドすることで、スエコザサを収穫する爽やかな季節を表現した。今は牧野植物園で「8種類のブレンドティー」を販売している。


■高知の良さ、もっと知って
「高知の生産者の思いを外へ伝えていきたい」。市吉さんは関東や関西の飲食店に高知の食材を卸し、街場ではマルシェを開催。生産者から預かった農作物をリプロダクトして届けている。コロナ禍には高知の間伐材を使ったキッチンカーを走らせて、マルシェや子ども食堂を開いた。10年にわたる経験の集大成となるのが、常設店舗の「the groceries shop Loka」。昨年9月に高知市の百貨店内でオープンした。
「仕事も遊びも一緒にする中で、いろんな人をそこへ巻き込んでいる」と言うだけに、中里自然農園の作物を最初に取り扱ったのも市吉さんだ。生物学の専門知識を生かしながら、独学で農業を始めた拓也さん。最初は販路もなく、人づてに市吉さんを訪ねていったという。東京勤務時代には「農家になるなんて1ミリも思っていなかった」という早紀子さんは、縁もゆかりもない安芸市での仕事を見つけて「スピード移住」。その後、ひょんなことから農園長の拓也さんと出会い「スピード婚」した。今では年間で「50、60種類、農薬とか化学肥料を使わずに育てています。県外への発送がメイン。個人宅への発送と、あとは飲食店に発送しています」。


■高知での暮らし、ここが変わった
高知に暮らし始めると、それまでの生活が大きく変わった。大阪勤務時代と比べて「オンとオフ」を切り替えなくなったと話すのは市吉さん。「こっちは暮らしの延長上に仕事があって、仕事の中に暮らしがある」。地元生産者の刈谷さんとは、趣味のサーフィンでも意気投合。「行ったら畑の横にスケートボードのランプがあった。もう最高なファーマー(農家)やなって」。仕事も遊びも一緒にする。取引相手ではなく、「マブダチ」として苦楽を共にする仲になった。
当然、「お金を稼ぐことが人生の成功」という価値観もガラリと変わった。「高知に来て生産者たちとつながると、その先には自然があって。その大きいサイクルの中の最後で、僕はお客様にそれを伝える役目を与えてもらったんやな、というのがすごく分かりました」
京都で「旬を追いかけていた」竹内さんは、「旬が追いかけてくるようになった」。「一時に白菜が採れる、一時に大根が採れる。それをどう食べていくか。アユも一時に取れますし」。高知は、川の幸である天然アユの宝庫だ。漁の解禁日は初夏。仁淀川では今年6月1日に解禁している。
「都会にはモノがたくさんありますよね。広告代理店だとそういうものを扱う仕事もしていて、それはそれで大事なことだと思うんですけど」と切り出したのは早紀子さん。「田舎に来て自分たちの食べるものを作り、塩を作り、はたまたイノシシのお肉を頂いたり。自分たちの体を作る『食』の重要性みたいなのをすごく感じています」。都会での生活では味わえなかった、季節とともに暮らす感覚に心地良さを感じている。「この時期にはこれをしなきゃいけない、この時期はこれがあるからこれをしようって、季節の中で生活を楽しむようになりました」

■最高の居心地、高知のここが好き
高知の気に入っているところについて、市吉さんは高知県人の暮らし方を挙げた。「しんどいところも共有して、作業を手伝わせてもらったりもしていて。(仕事とプライベートを)分けてしまっていたら、こんなに仲良くなれてなかったかもしれない。そういう彼らの暮らし方に最高にほれ込んでいる感じ」。「人がおおらかっていうのが一番の魅力かな。何があっても、お酒を飲んで忘れる文化」と話すのは拓也さん。「ラテン系」の明るい気質で、お酒の席も盛んに開かれている。
もちろん自然の魅力も欠かせない。「84%が森林」で、海に面して広い浜があり、そこに川が何本も注ぐ。竹内さんが挙げたのは、「海山川がそろっている」だけに「素材がたくさん」あること。「食べ物がおいしい。お酒がおいしい。それに尽きるかなと思います。おいしいものが順次、目の前の山から出てくる。目の前の川から出てくる。そういう豊かさがありますね」。都会育ちの中里さん夫婦も、自然の魅力を挙げた。「海も川も山も、ギュっとコンパクトに集まってるのが魅力。旬のものを、旬の時に食べるのが農家の楽しみですね」


■未来にバトンをつなぐ、高知でのこれから
2013年に移住してから10年。移住後すぐに出会いがあり、2人の子どもにも恵まれた。「まさか家庭を持って根を張るとは、来る時は思ってなかったんですけど。今考えると運命的なものがあったんやろうな」。生きる「時間軸が変わった」と話す市吉さん。「暮らしを次の世代にバトンしていく、子どもらの未来に何を残してあげるか」。そんなふうに思うようになったのも、農家の暮らしぶりを身近で体験したから。「農家と話していると、何十年先を見て畑を耕しているのが分かったし、そういうことが大事だなと思った」
「大きく跳ねるようなことはしたいとは思いません。できるだけ長く続いていく商いをやっていきたい」と話すのは竹内さん。「山間ですので、またさっと出て行くとか・・・。移住者っていう言葉の中に、マイナスの意味も含まれている気がするんです」。だから、竹内さんは自分を移住者と呼ばない。「引っ越しさせていただいて、みんなが元から住んでいた場所でなじませていただいて、長く商いを続けていく。年輪のようにじわじわと広げていくやり方でやっていきたいですね」
最近は「農園に行きたいというアプローチをいただくことが多い」と教えてくれたのは中里さんご夫婦。今も、大学生が1週間滞在しているという。「農家のこと、暮らしのことが、誰かのヒントになればいいなと思っています。みんなが集える農園にしていきたい」と言うのは早紀子さん。若い人が「都会の生活をしていて疑問に思うところが結構ある。田舎の生活を体験してみたいと思うのではないか」と拓也さん。「生きていく力」を身に付ける修行を続けながら、「次の世代に、教えるって言うとおこがましいんですけど、何か感じてもらえるような機会を作っていきたい」。