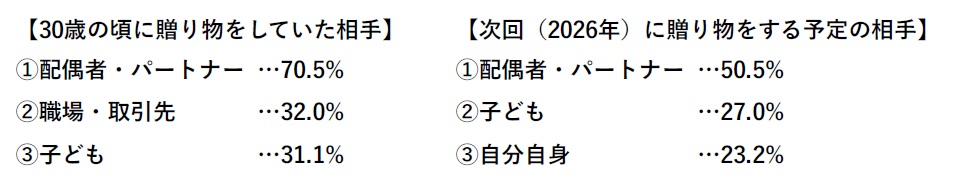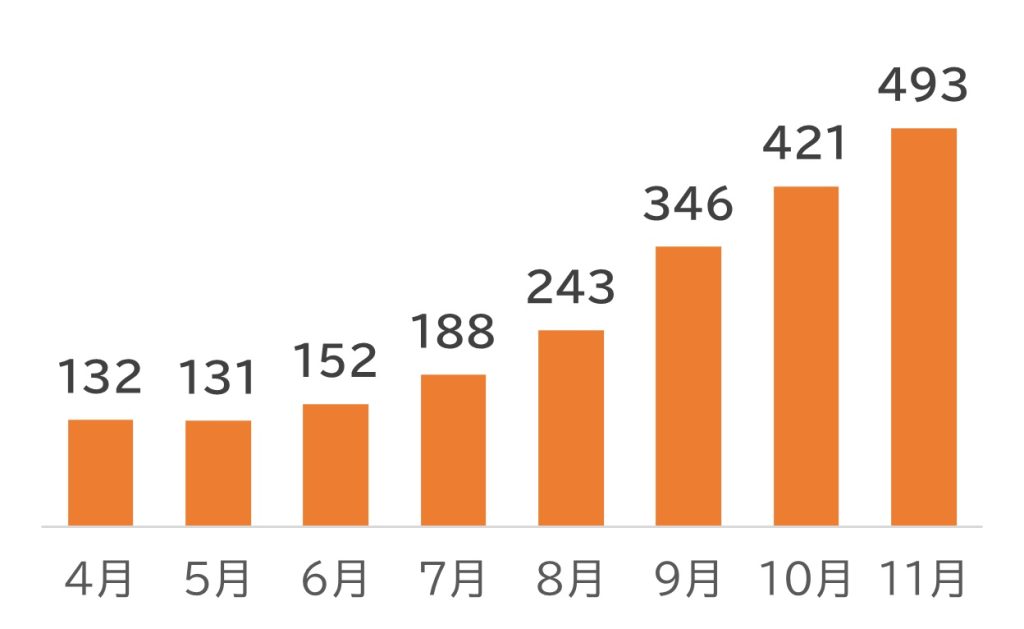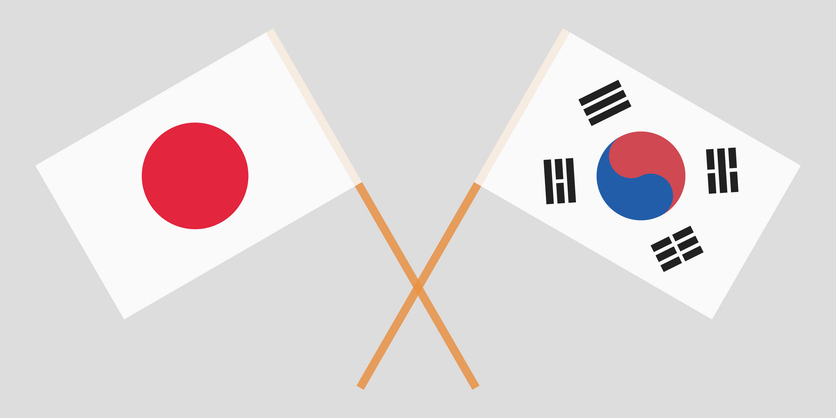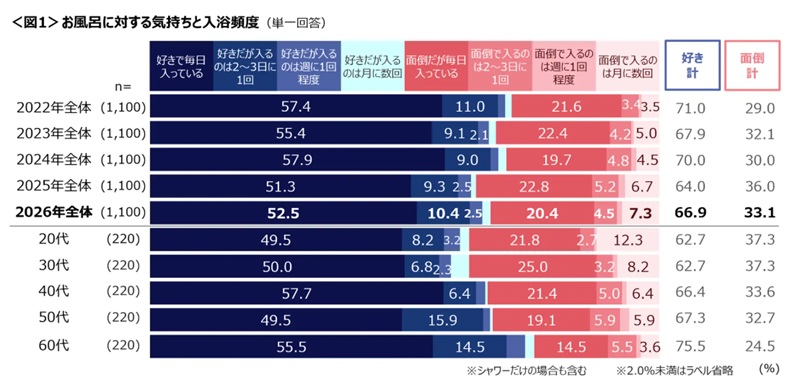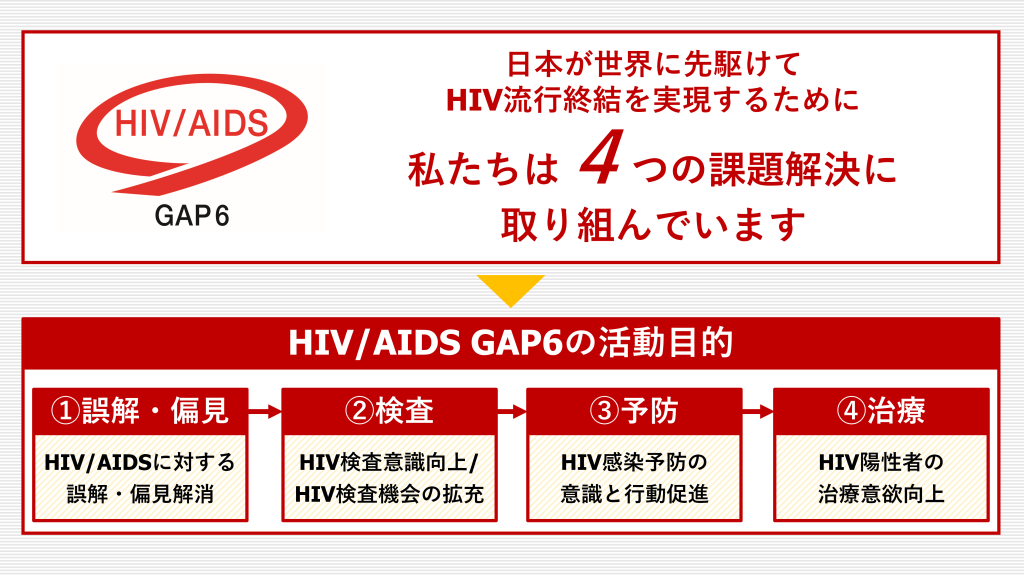祖父の他界後、大学生の拓磨は、夫に先立たれて独り残された祖母・文子と同居することになった。ある日、拓磨は亡き祖父・偉志の書斎で、大学の入学案内を見つける。それは偉志が遺した妻・文子へのサプライズだった。市毛良枝とグローバルボーイズグループ「JO1」の豆原一成が、同じ大学に通うことになった孫と祖母を演じる『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』が10月24日から全国公開される。44年ぶりの映画主演となった市毛良枝に話を聞いた。

-今回、演じる上で気を付けたことや心掛けたようなことはありましたか。
私は、割とお相手の方との空気感で役を作っていくタイプなので、あまり理屈を考えないというか。この役はこういう人という理解はしますけど、相手役の方が変わればそれも変わってしまうので、その方の声を聞いて、自然に自分の音程が決まってくるみたいなところがあるので、ずっと自然にやらせていただきました。
-そういう意味でも、夫役の長塚京三さんとの共演はいかがでしたか。
長塚さんとはちょっと別の物語があって。この映画では50年目の夫婦の役ですけど、そのスタートのような作品が別にありました。私もまだ若かったし、長塚さんもフランスからお帰りになってすぐくらいで、日本でのお仕事はまだそんなにされてない頃に、恋人から結婚するという話を一緒にやりました。それが私の中に記憶として根強く残っていたので、その方と50年後に50年たった夫婦の役をやるのはすごくありがたいなと思いました。そうしたら、同じことを長塚さんが言ってくださって。だから文子さんが偉志さんをとても愛している雰囲気が自然に出てきた感じでした。
-では、孫役の豆原一成さんの印象はいかがでしたか。
クランクインする前は彼のことを全く知らなくて、「JO1ってすごいグループの子なんですよ」と言われても、そうなのね、くらいでした。だからバリバリのアイドルさんが来られるのだろうとイメージしていたら、すごくかわいらしい普通の青年が現れて、普通にお話をして、普通になじんでしまいました。もちろんかわいいからアイドルだというのは納得できるんですけど、アイドルをしている姿が撮影中は思い浮かばなくて。夜に「これからアイドルしに行ってきます」とか聞くと、今からまた仕事、大変だなみたいな感じでした。ある時たまたまテレビにJO1が出ていたのですが、ほんとにアイドルでした。
-文子のキャラクターをどう捉えましたか。
文子さんは幸せな人ですよね。夫にあんなに愛されて。それがすごくうらやましいと思いました。もちろん、夫が存命中も幸せだったと思うんですけど、その頃は夫の世界だけで生きてきた人だったと思うんです。でも、その時間があったおかげで今羽ばたけていると思うから、すごく幸せな人だと思います。
-そうした思いを踏まえて、文子をどのように演じたのですか。
私は自分の母をイメージしました。大正の初期の生まれだったので、いわゆる“日本の母”というふうに見せていましたけど、実はそうではなかったらしくて。60歳ぐらいから、背負っていたものを脱ぎ始めて、最終的には自由奔放でわがまま放題みたいになったんです。でも、どこに行ってもいろんな友達を作ってきて、知らない人がうちにいたりしました。その人たちとも長くお付き合いをしていましたし、どこに行ってもすごく愛されていて。そういう社交的な母だったので、イメージしながら文子さんを演じました。