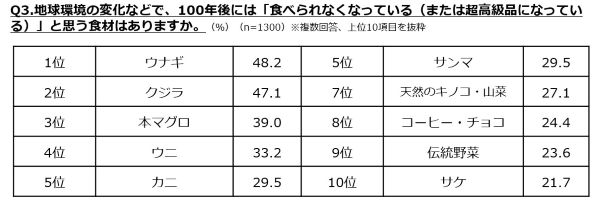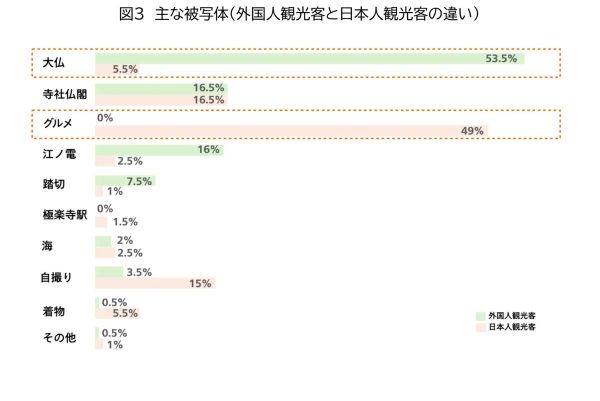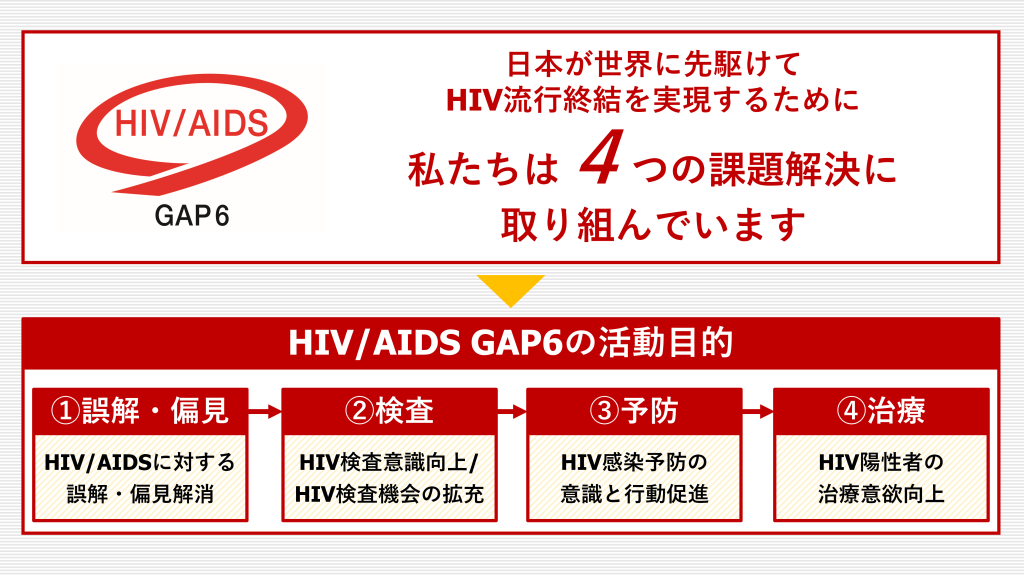-そう考える理由は?
「ごっこ遊び」と言いながら、そこに本当の気持ちを込めることができるのが演劇です。それによって、人間は一つ脱皮できる気がします。しかも、最終的には「うそです」と言える逃げ道も用意されている。人って、どこかで役割を演じて生きていますが、それを全うできず、つらくなる時もあると思うんです。でも、演劇にはきちんと終幕があるので、演じ切ることができ、カタルシスを得られる安全性がありますし。
-なるほど。
だから、素人の方にこそ、演劇をお勧めしたいですし、かつて蜷川(幸雄)さんが立ち上げたように、シニアの市民劇団がもっと増えてもいいんじゃないかなと。この作品を経験し、さらに強くそう思うようになりました。
-市民劇団を舞台にした本作を通じて、内野さんご自身の演劇に対する考え方が影響を受けた部分はありますか。
僕も含め、プロの俳優はキャリアを重ねると、「らしく」見せるテクニックをたくさん持つと思うんですけど、お客さんが感動するのは、そこではないんですよね。その裏に、その人自身が持つ心の真実が重なったとき、迫真性が出て、すさまじい表現になる。僕も蜷川さんの舞台でシニアの役者の方とご一緒したことがありますが、長年の人生経験から醸し出される深みや味わいには、せりふなんか必要ないくらいの説得力があるんです。だから、いくら熟練しても、それに安住しないエネルギーが必要になる。演技にとって大事なそういったことを、改めて思い出させてくれました。
-全6話を通して、阿久津とつらい過去を秘めた中学生・上村琴音の交流が描かれるのも本作の見どころです。琴音を演じるのはNHKの連続テレビ小説「おちょやん」(20~21)や「虎に翼」(24)でも活躍した毎田暖乃さんですが、共演はいかがでしたか。
阿久津は不愛想な男ですが、実は子どもながらに自分と似た境遇を抱える琴音を見守る優しさを秘めています。ただ、外界と語れないという大きな足かせがあったので、その気持ちをどう表現すればいいのか、だいぶ悩みました。言葉といえば、「リア王」のせりふしか出てこない人ですから。最終的には、彼女の前で、必死に戦っている老いた姿を見せることだなと思ったので、彼女との触れ合いは言葉を超えたものだったような気がします。役柄的なこともあり、僕自身は現場で毎田さんとあまり話はしませんでしたが、大変な役にもかかわらず、くじけずに頑張っている彼女の姿に、大いに刺激を受けました。

-シリアスな物語でありながら、阿久津と琴音の間にユーモラスな空気が漂っているあたり、人間味があふれていて、親しみを感じます。
シナリオの時点から、2人の間にユーモラスな匂いが感じられたので、そこは大事にしたいと思っていました。
-年の離れた阿久津と琴音の交流を通じて、どんなことを感じましたか。
最初に大森監督から「若い世代へ受け渡していく話」とお聞きし、僕自身もふに落ちるものがありました。ただし、「受け渡す」からといって、抜け殻になるのではなく、最後まで熱量高く生きざまを見せていかなければいけないなと。50代に入って僕も、周囲からベテラン扱いされる機会が増えてきました。でも、そこにあぐらをかくことなく、新人に負けないくらいの魂でぶつかっていかなければ、見ている人は納得しませんよね。逆に、たとえ新人の方と芝居をするときでも、きちんと1人の役者さんとして向き合わなければ、と思っています。
-まさに、阿久津と琴音の関係にも通じるお話です。
世の中に完璧な人間はいません。それでも、親や先輩が踏ん張りながら生きる背中を見て、若い人は何かを感じとっていくんじゃないかと思うんです。だから、立派なアドバイスはできませんが、僕自身も苦闘しながら生きていくしかないのかなと。その点、この作品も僕にとっては挑戦だったので、できるだけ多くの方にじっくり味わっていただきたいですし、ご覧になった皆さんの忌憚(きたん)のないご意見をぜひお聞きしたいです。
(取材・文・写真/井上健一)