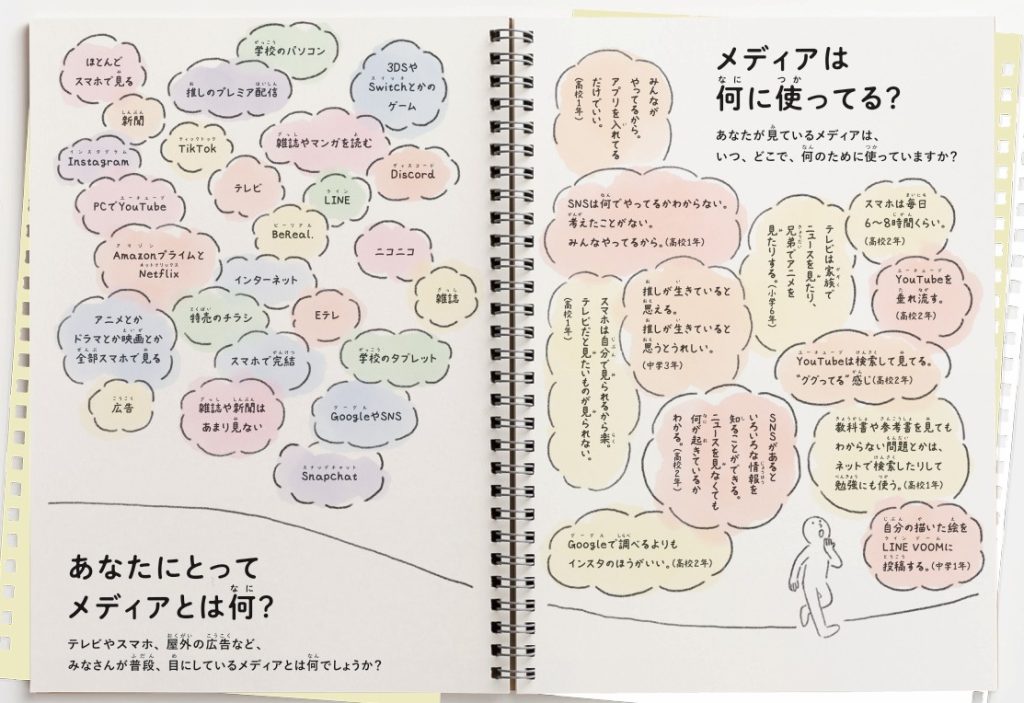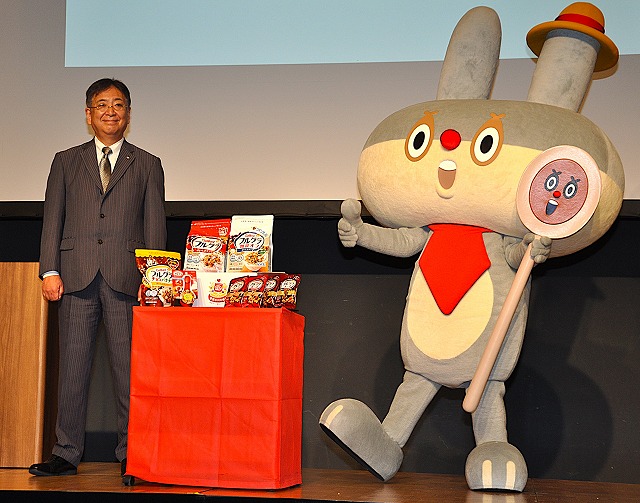「人生の3分の2はいやらしいことを考えてきた」。
これは、みうらじゅん氏の週刊文春での連載コラム「人生エロエロ」の書き出しだ。夏目漱石風のこの文章が気に入っている。そして私もその仲間だなと思うのである。
ビートルズの4人も少なくとも若いころはその類いだったようだ。

ビートルズの広報担当だったトニー・バーロウ氏は内幕を描いた「ビートルズ売り出し中!」(河出書房新社)という本で次のように書いている。「1962年当時のどんな盛りのついた元気で素直な男の子とも同じように、ビートルズの面々も、自分たちが初めて経験したおぼつかないセックスの冒険譚を友だちと自慢しあったりしていた」。
彼らは62年のデビュー以来、男女関係についてこれでもかこれでもかというほど歌にした。「抱きしめたい」(アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユア・ハンド)では「あなたの手を握りたい」と彼女にせまり、「オール・マイ・ラビング」では「目を閉じてごらん、キスしてあげる」とくどくなど、男女間の恋愛、性愛願望を歌ったのである。
転機となったのが65年に発表された「イン・マイ・ライフ」ではないだろうか。ジョン・レノンはこの曲で思い出の場所を「今でも思い出す恋人たちや友人たち」とともに回想し、「ぼくの人生で、生きていようと亡くなっていようとかまわない、彼らみんなを愛する」と歌ったのである。もう愛はぼくと彼女の間だけではないということなのだ。
よく英語の歌では「belong」(属する)という単語を使った「彼女はぼくのもの」とか「ぼくが君のものになるまで」とか、そういう表現が見受けられる。ビートルズも若い時はそういう表現が満載の曲を書いていた。しかし、そういう男女間で互いに相手を「もの」として「所有」しているかの表現は次第に影を薄めていくことになる。
物質社会における男女関係とは、恋愛とは、愛とはといったことを考え始めたのだろう。
その現実社会における男女関係とはという問いを投げかけてくる歌が、80年のジョン生前最後のヒットシングル「スターティング・オーバー」だと思う。

この曲は5年間の「主夫生活」を送ったジョンが、彼と妻のヨーコ・オノの再出発を高らかに歌い上げるというものだったが、歌詞を読むと「なぜ、私たちは一人ぼっち(alone)で、どこか遠くに、旅立てないのだろうか?」とか、「私たちは独力(on our own)で再び一緒(together)になれるだろう」など再出発の歌にしては「暗い」。

「ビートルズ大学」(アスペクト)の著者である宮永正隆氏は「ジョンが自分の死を予言していたとしか思えない詩」だと指摘した。
確かに「一緒に飛び立とう」ではないのである。
「一緒」というのが魂や肉体が近くにあるという意味であるのなら、結局は魂、肉体はそれぞれ元々単体のものなのではないだろうか。とすれば「一緒」というのは少なくとも現生においては「かりそめ」なのではないだろうかと思う。よく言われるではないか、「人は生まれるときも一人、死んでいくときも一人」と。
少し「寂しい」感じもするが、ジョンの歌が残した謎についてはそのように考えている。
男女関係も含めて人間関係はそんなにきれいごとばかりではないと思う。たしかに、ビートルズの4人もそれぞれ離婚を経験している。
90年代に入り、ジョンが残したデモテープをもとに、他の3人が参加して、「新曲」が2曲制作され発表された。「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラブ」である。最後のメッセージが「自由」と「真実の愛」というのがビートルズらしいではないか。「リアル・ラブ」では「もう一人ぼっち(alone)になる必要なんてない」と歌われている。
真実の愛があればということなのだろうか。
(文・桑原 亘之介)
桑原亘之介
kuwabara.konosuke
1963年 東京都生まれ。ビートルズを初めて聴き、ファンになってから40年近くになる。時が経っても彼らの歌たちの輝きは衰えるどころか、ますます光を放ち、人生の大きな支えであり続けている。誤解を恐れずにいえば、私にとってビートルズとは「宗教」のようなものなのである。それは、幸せなときも、辛く涙したいときでも、いつでも心にあり、人生の道標であり、指針であり、心のよりどころであり、目標であり続けているからだ。
本コラムは、ビートルズそして4人のビートルたちが宗教や神や信仰や真理や愛などについてどうとらえていたのかを考え、そこから何かを学べないかというささやかな試みである。時にはニュースなビートルズ、エッチなビートルズ?もお届けしたい。