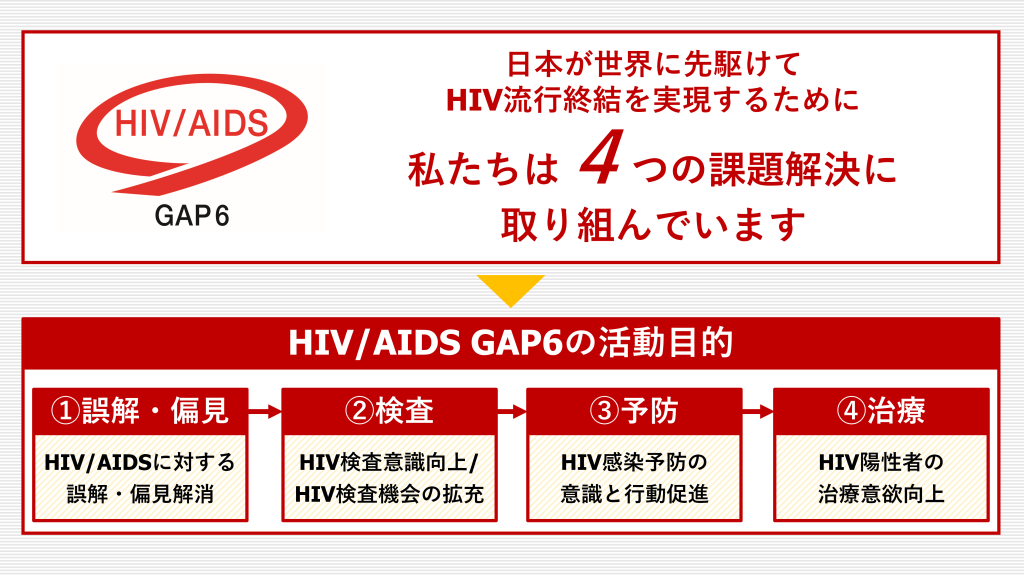山崎 雅弘
日本国は、民主主義国である。
この国に住む人の大多数は、おそらく漠然と、そんなふうに理解していることだろう。
だが、本当にそうなのだろうか? われわれが住む日本は「近隣のあの国とは違う民主主義国である」と、大した根拠もないままに信じ込んでいるだけではないだろうか?
権力を握る政府トップや支配政党が、国民や議会の意見をろくに聞かないまま、重要な政策転換の決定を次々と下す。議会では、議席数の優位にあぐらをかき、不誠実な答弁とはぐらかしで時間を費やして「議論がなされたというアリバイ」を作る。国民の批判は一顧だにせず、政府側の建前を機械のように一方通行で繰り返して「丁寧に説明した」と言う。
こんな国は、果たして「民主主義国」と呼べるのだろうか?
例えば、2022年11月から12月にかけて慌ただしく既定方針化された、この国の防衛政策の大転換。そこで決定された「外国攻撃能力の保有」は、憲法9条で「永久にこれを放棄する」と明記された「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を実行可能にする内容である。言い換えれば、憲法9条は実質的に空文化した。
だが、この歴史的な防衛政策の大転換は、国民的議論と国会での熟議を経てなされたものではない。まず、11月22日に「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」と称する首相直属の諮問会議が、岸田文雄首相に報告書を提出したが、その中には「防衛費の大幅増額と増税を含めた国民負担」や「外国攻撃能力の保有」が明記されていた。
これを受けて、岸田氏は12月16日に「国家安保戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の安保3文書を閣議決定し、外国攻撃能力保有を事実上肯定した。岸田氏は「今後も専守防衛の姿勢は変わらない」と取り繕いの言葉を並べたが、論理的に考えれば、相手国への攻撃能力の保有それ自体が、専守防衛という戦後日本の国是の放棄を意味する。
この重要な決定プロセスにおいて、一般国民の意見や議会(国会)での熟議は事実上無視された。岸田内閣の閣議決定を、大手メディアは〝政府の決定事項〟のように報じ、憲法9条の空文化という重要な政治的意味を持つ論点から国民の目をそらすかのように、報じる際の重点は「防衛費増額を何で賄うか、増税か国債か」という財源論に置かれ続けた。
国会での議論は、閣議決定の内容を追認する儀式のようになされ、国民はいつものように、木で鼻をくくったような政府側の言い分を「丁寧に説明」されただけだった。
こんなことがまかり通る国が、果たして「民主主義国」を名乗れるのだろうか?
「権威主義国」に逆戻り
戦後の日本が目指してきた民主主義国とは、こういう国ではなかったはずだ。
明治維新で江戸幕府が倒され、日本は欧米式の近代化を進めてきたといわれるが、今の日本における政治決定のプロセスは、ほとんど幕府のそれと変わらないのではないか?
敗戦翌年の1946年5月から47年2月にかけて、文部省(現在の文部科学省の前身)が発行した教職員向けの参考書「新教育指針」には、次のような記述があった。
「上の者が権威をもって服従を強制し、下の者が批判の力を欠いて、わけもわからずに従うならば、それは封建的悪徳となる。事実上、日本国民は長い間の封建制度に災いされて『長いものには巻かれよ』という屈従的態度に慣らされてきた。いわゆる『官尊民卑』の風(ふう)がゆきわたり、役人はえらいもの、民衆は愚かなものと考えられるようになった」
戦後の日本は、大日本帝国時代の社会を支配した、封建的で非民主的な「権威主義」を排することで、民主主義国に生まれ変わろうとした。確かに戦後のある時期まで、国民は真面目にこの路線で努力を重ねてきた。ところが、気が付いてみると、現在の日本はここで指摘されているような、封建的で非民主的な「権威主義国」に逆戻りしている。
一体なぜ、こんなことになってしまったのか?
日本でよく見られる誤謬(ごびゅう)の一つに、民主主義の反対は何かという問いがある。
民主主義の反対は「共産主義」であり、日本は「共産主義国ではない」から民主主義国だ、という誤謬は、20世紀後半の東西冷戦期からしばしば語られてきた。だが、実際には「共産主義国か、民主主義国か」という対比は「誤った二元論」である。特定の結論に受け手を誘導する目的でなされる「誤った二元論」は、詭弁(きべん)の一つと分類される。
本来、民主主義国と対比すべき相手は「非民主的な権威主義国」であり、そこではイデオロギーの右派や左派は関係ない。共産党独裁国も、親米反共右派独裁国も、どちらも民主主義を否定する「非民主的な権威主義国」である。
現実には首相と内閣が独裁的に政策決定を行っているのに、「有識者会議」と称する首相直属の諮問機関による提言に耳を傾けたという体裁で責任の所在をうやむやにし、報道メディアも「閣議決定」を「お上のお触れ」のように無批判で広報宣伝するのが当たり前となった国は、民主主義とはかけ離れた「非民主的な権威主義国」だろう。
日本は「選挙で政治家を選んでいるから民主主義国だ」というのも、よくある誤謬の一つである。選挙とは、単に「議会の代表者を選ぶプロセス」でしかなく、特定の政策への賛否を表明する手段としては、きわめて不完全である。民主主義が成熟した国では、その不完全さを補うために、市民のデモや集会、ストライキなどの手段が社会的に尊重されているが、今の日本社会ではこれらの手段を尊重する気風がきわめて弱い。
もう一つ、「多数決で物事を決めるから民主主義だ」という認識も誤謬である。実社会でもネット上の世論でも、多数派は金と権力である程度は作り出せるが、多数派による少数派の圧迫と抑圧は、「少数派の意見や権利も尊重しなくてはならない」という民主主義の本来の理念とは正反対だからである。ところが、今の日本では、与党支持者を中心に、この誤謬を振りかざす論者が多い。彼らは平気で、少数者をないがしろにする。
個人として思考・行動を
日本語の「民主」という言葉は「民が主」と書く。
主とは「ぬし」や「あるじ」との意味だが、社会の主体や主役とも解釈できる。
民主主義=デモクラシーとは、古代ギリシャ語で「民衆」を意味する「デーモス」と、権力を意味する「クラトス」を組み合わせて作られた「デモクラティア」を語源とする概念で、日本語の「民主主義」もおおむね原語の意味を正しく反映した言葉だといえる。
戦後の日本社会が、民主主義国としての成熟を目指す努力を緩やかに停止し、戦前や戦中の大日本帝国に似た「非民主的な権威主義国」への道を逆戻りし始めた理由の一つは、国民が自分を社会の主体や主役と捉える意識が薄れたことだろう。
戦後の学校教育も企業や官庁の組織文化も、民主主義の「形式」は建前として尊重しつつも、実質では上位者への服従を基本原理としてきた。集団内で波風を立てず、秩序を乱さないことが良しとされ、個人としての主権者意識はそれの邪魔になると考えられた。
だが、今後もそのような「上位者への服従」ありきの社会でいいのだろうか。
先に引用した「新教育指針」の文言を、もう一度読み返していただきたい。この国に破滅をもたらした大日本帝国時代の精神文化と、今の日本はそっくりではないか。
それでは、日本の社会が再び民主主義国を目指すためには何が必要なのか。
第一に必要なのは、各人が勇気を持って「個人として思考し、行動する」ことである。第2次大戦中、ナチ親衛隊の管理職としてユダヤ人大量虐殺「ホロコースト」を加速させたアドルフ・アイヒマン(1906〜62)のような「上位者への盲目的服従」や、集団内の同調圧力に思考と行動を追従させるような態度は、民主主義を衰弱させ、枯れさせる効果を生み出す。
次に必要なのは、政府が打ち出すあらゆる政策について、それが「人を大事にするものか、それとも人を粗末にするものか」という尺度で判断し、後者であるなら徹底的に批判することである。人権や人道の尊重が、政府の政策における優先順位の上位にあるかどうかで、その国が民主主義国であるか、それとも「非民主的な権威主義国」なのかを判別できる。
われわれ大人が自国を民主主義国にするための「不断の努力」を怠れば、後の世代は今よりもさらに非民主的な「権威主義」で心身を圧迫され、思考と行動が萎縮していく。それがエスカレートすれば、戦争などに起因する生活環境の悪化が現実のものとなる。
子どもたちが苦しまず、笑顔でいられるか否かは、大人の態度にかかっているのである。
戦史・紛争史研究家 山崎 雅弘(やまざき・まさひろ) 1967年大阪府生まれ。古今東西の戦史・紛争史を多面的に分析する著述活動のほか、時事問題に関する論考を新聞・雑誌・インターネット媒体などに寄稿。「アイヒマンと日本人」(祥伝社新書)、「太平洋戦争秘史」(朝日新書)、「沈黙の子どもたち」(晶文社)、「未完の敗戦」(集英社新書)、「この国の同調圧力」(SB新書)など著書多数。趣味は旅行、美術・博物館巡り。
(Kyodo Weekly 2023年8月14日・21日号より転載)