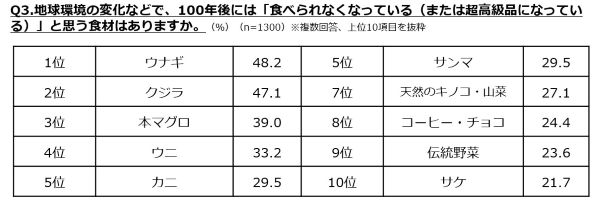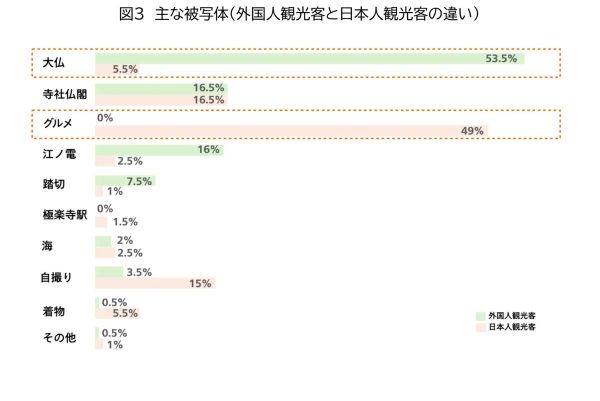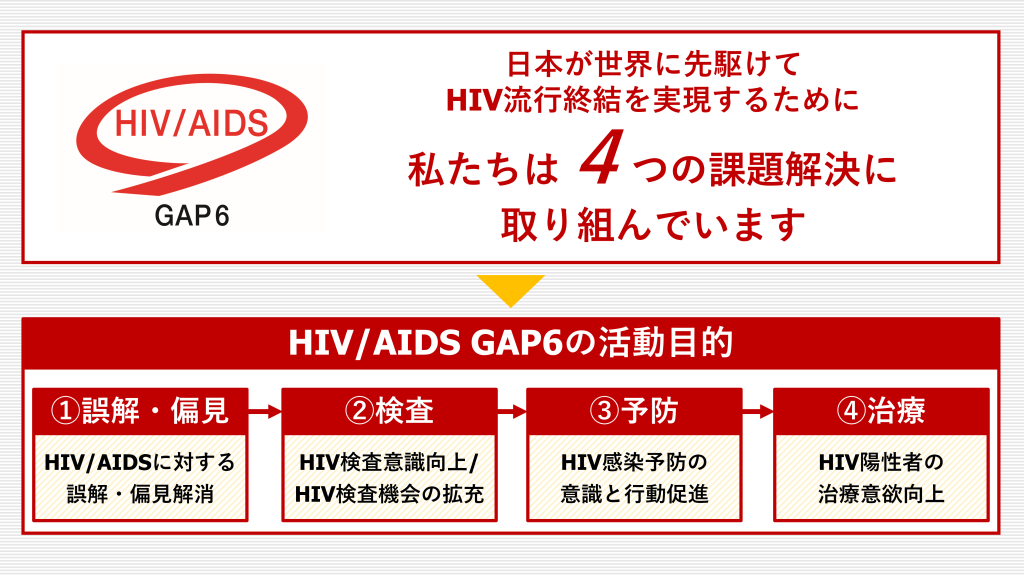『オッペンハイマー』(3月29日公開)

才能にあふれた物理学者のロバート・オッペンハイマーは、第2次世界大戦中、核開発を目的とした米政府のマンハッタン計画において、原子爆弾開発プロジェクトの委員長に任命される。
だが、実験での原爆の威力を目の当たりにし、さらには日本の広島と長崎に投下された原爆による恐るべき惨状に衝撃を受けたオッペンハイマーは、結果的に大量破壊兵器を生み出してしまったことを悔い、戦後は水素爆弾の開発に反対するようになる。そんな中、彼にソ連のスパイ容疑がかかり、公聴会に召喚される。
『ダークナイト』(08)『インセプション』(10)『インターステラー』(14)『TENET テネット』(20)など、話題作を送り出してきたクリストファー・ノーラン監督が、“原爆の父”と呼ばれたアメリカの物理学者を題材に描いた伝記映画。
2006年にピュリッツァー賞を受賞した、カイ・バードとマーティン・シャーウィンのノンフィクションを下敷きに、オッペンハイマーの栄光と挫折、苦悩と葛藤を描く3時間の大作だ。
オッペンハイマー役はノーラン作品常連のキリアン・マーフィー。彼の妻キティをエミリー・ブラント、原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・Jr.、マンハッタン計画の指揮を執る軍人レズリー・グローブスをマット・デイモン、アルバート・アインシュタインをトム・コンティが演じたほか、ラミ・マレック、フローレンス・ピュー、ケネス・ブラナー、ケーシー・アフレックら、豪華キャストが共演している。
撮影は『インターステラー』以降のノーラン作品を手がけているホイテ・バン・ホイテマ。音楽は『TENET テネット』のルドウィグ・ゴランソンが担当。
アカデミー賞では、作品賞、監督賞(ノーラン)、主演男優賞(マーフィー)、助演男優賞(ダウニー・Jr.)のほか、計7部門で受賞した。
ノーラン監督にとっては、『ダンケルク』(17)に続く実話を基に描いた映画。その『ダンケルク』は、陸海空とそれぞれ異なる時間軸の出来事を一つの物語として同時進行させた視点が目を引いた。
今回も時系列を崩してオッペンハイマーにとっての現在である公聴会の様子と、マンハッタン計画などの過去、そして対立するストロースの様子(モノクロ映像)が交錯する作りになっている。その点で、この映画も時間の流れや記憶にこだわり続ける、紛れもない“ノーラン印の映画”ということができる。
オッペンハイマーはギリシャ神話に登場する火の神プロメテウスに例えられる。この映画でも「原爆投下が戦争を終結させた」というアメリカ側の論理が語られる場面があるが、決してそれを肯定してはいない。むしろ予想以上の被害の大きさを知らされておののく人々の姿も描かれる。
「爆弾を作ってノーベル賞か?」(グローブス)「アルフレッド・ノーベルはダイナマイトを発明したじゃないか」(オッペンハイマー)という皮肉っぽいせりふのやり取りがあったが、学者としての研究開発への欲望と、結果的に大量破壊兵器を作ってしまった後悔という二律背反するジレンマが、オッペンハイマーという人物を描く上での根幹になっている。
そして、原爆の開発は、対日本というよりも、対ナチスドイツを念頭に置いたものだったこと。だからこそユダヤ人であるオッペンハイマーは必要以上にのめり込んだ。あるいは、戦後のソ連との冷戦構造による反共、赤狩りの犠牲者としての側面など、知られざるエピソードが描かれ、興味深いものがあった。
また、オッペンハイマーは、ある意味、変人であったという点では、“コンピュータの父”と呼ばれたイギリスの数学者、アラン・チューリングを描いた『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』(14)とも通じるものがあると感じた。
原爆を投下された日本では、“原爆の父”を描いた映画だけに公開が危ぶまれたが、一方的にではなく、多面的な要素から原爆開発を捉えたこうした映画こそきちんと見せるべきだと感じていたので、公開は喜ばしい。