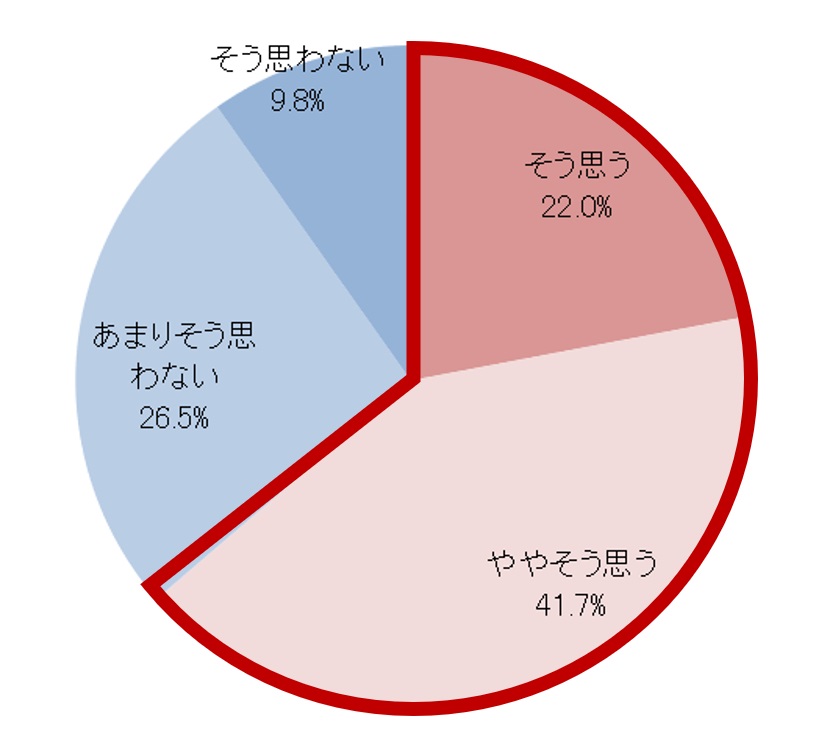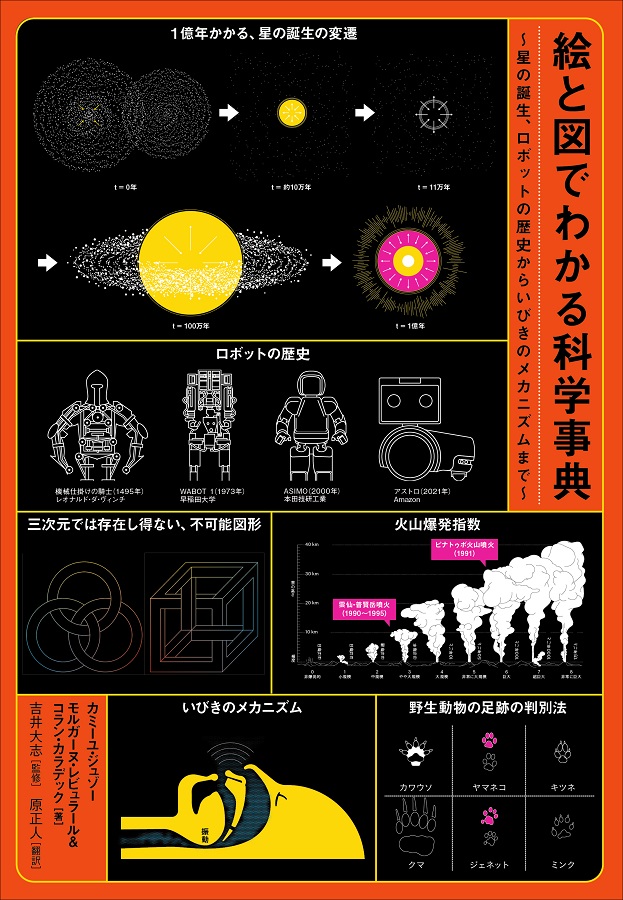“I live in Tokyo”の過去形は何ですか?
ある人の答えは、“I live in Edo(江戸)”。ここで動詞の過去形うんぬんと言って説明するか、それともこれでも正解と答えるか、あなたが先生だったらどうしますか?
問題は想像力(創造力)に関わってくる。「イマジン」を歌い、想像することの大切さを訴えたジョン・レノン。彼の死後も「想像」の持つパワーを説いてやまない妻オノ・ヨーコ。ジョンは同時に行動の人でもあった。もちろんヨーコも。
70年代前半、ジョンはFBI(米連邦捜査局)から尾行、盗聴されていた。彼とヨーコの新左翼のリーダーたちとの接触が米当局の気に障ったからである。そして76年7月にアメリカ永住権(グリーンカード)が認められるまで、米政権との闘いが続く。70年代前半当時はベトナム戦争に対する反戦運動の高まり、公民権運動のあとの人種間の争いの高まりなどを背景に、ジョンとヨーコは「政治の季節」の真っただ中に躍り出ていた。
ジョンとヨーコが恐れられたのは、人気・影響力絶大な彼らが「裸の王様」を見抜く能力に長け、本当のこと、つまり真実を話し、歌ったからだと考えている。そして、理想と現実のギャップを埋めるのが政治の仕事だととらえ、ベクトルが理想に向かっていないものたちに対して、2人は容赦なかったからである。
ジョンの71年の作品に「兵隊にはなりたくない」がある。「兵隊にはなりたくない、母さん、死にたくない」という歌詞の作品は、ベトナム戦争を推し進めていた当時のリチャード・ニクソン米大統領らを当惑させたに違いない。

ジョンはかつて言った。「直接(ぼくたちは)政治に関わっていないけれど、ぼくがやることは、最終的に政治に関係する。でも、これは誰にでもいえることだ。いかなる発言、記録、そして生き方さえもが、政治的な態度表明なのだ」、「愛、平和、コミュニケーション、ウーマン・リブ、人種差別、戦争。ぼくたちがこれから話しあいたいのは、こういうテーマだ」(ジェイムズ・A・ミッチェル著「革命のジョン・レノン」共和国刊)。
彼らの政治への関わりのピークといえるのが、72年発表の二人のアルバム『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』である。黒人に対する人種差別に対するプロテストソング「アッティカ・ステート」や、マリファナ2本の所持で禁固10年を言い渡された活動家の釈放を求めた「ジョン・シンクレア」、女性差別解消の必要を訴えた「女は世界の奴隷か」など、政治的メッセージソング満載の作品である。アルバムジャケットにはニクソン大統領と中国の毛沢東主席の裸踊りの合成写真が使われていることも話題となった。
もしジョンが生きていたらという歴史のIfを口にする人が少なくない。
1980年12月8日、ジョンは凶弾に倒れた。40歳だった。75年から「主夫」生活を送っていた彼が音楽活動を再開した矢先だった。そして彼は政治からも手を引いたわけではなかった。政治的活動も再スタートさせようとしていたのである。

米西海岸で白人に比べて賃金などの待遇で差別されていた日系アメリカ人労働者たちを支持する声明を送ったばかりで、ジョンが凶弾に倒れたまさにその週の内にも、彼とヨーコは息子ショーンを連れて、サンフランシスコで行われる集会に参加する予定だったのだ(ジョン・ウィナー著「カム・トゥゲザー ジョン・レノンとその時代」PMC出版)。
問題企業の中にはしょうゆで知られる日本のキッコーマンが経営参画する米国最大の日本食品商社JFCと他の日本人所有のふたつの会社があった。そしてウィナー氏は、そういった労働争議の渦中にあった企業に対しては「南カリフォルニアにおける日本人ビジネスマン団体」や「三菱」、「住友」といった財閥の「実質的支援があった」と指摘した。ちなみにヨーコは安田財閥の出である。
カリフォルニア州知事を長年務めたこともあり、当時は第40代米大統領への正式就任を待つばかりだった共和党のロナルド・レーガンのお膝元である。レーガンといえば、反共、反ソを標ぼうするゴリゴリの保守主義者として知られた。
ジョンの「不可解」な死の背後にレーガンの影を見る人も少なくなかったのである。
政治的活動を再スタートさせようとしていたジョンとヨーコ。彼らはショービジネスの世界でも本格的に「スターティング・オーバー」(再出発)する矢先だった。ジョンが亡くなっていなければ、彼はヨーコとともに81年3月から日本を皮切りとしたワールド・ツアーに出る予定だった(80年12月10日付日刊スポーツ)。
ジョンとヨーコは、移籍先のゲフィン・レコードを通じて、ビートルズ来日を実現させたことでも知られる日本の凄腕興行師である永島達司氏に強く要請してきていた。「(81年)3月4日初日の日本武道館公演5回と大阪を中心に、ヨーコ本人の『広島、京都でもやりたい』との希望も入れて10回の全国公演を予定。あとはレノン側からのOKサインが出るのを待つばかりだった」という。
(文・桑原 亘之介)
桑原亘之介
kuwabara.konosuke
1963年 東京都生まれ。ビートルズを初めて聴き、ファンになってから40年近くになる。時が経っても彼らの歌たちの輝きは衰えるどころか、ますます光を放ち、人生の大きな支えであり続けている。誤解を恐れずにいえば、私にとってビートルズとは「宗教」のようなものなのである。それは、幸せなときも、辛く涙したいときでも、いつでも心にあり、人生の道標であり、指針であり、心のよりどころであり、目標であり続けているからだ。
本コラムは、ビートルズそして4人のビートルたちが宗教や神や信仰や真理や愛などについてどうとらえていたのかを考え、そこから何かを学べないかというささやかな試みである。時にはニュースなビートルズ、エッチなビートルズ?もお届けしたい。