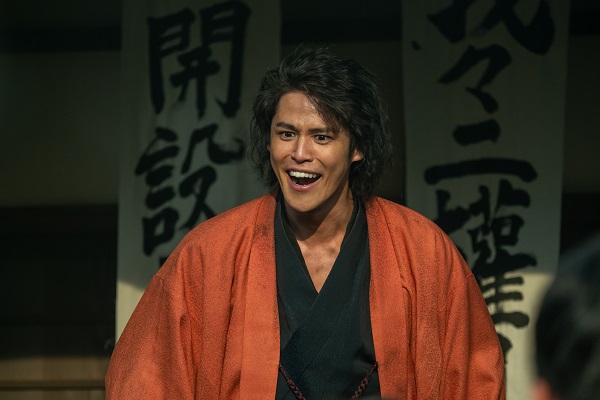ポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一が初めて手掛けるオリジナルミュージカル、a new musical「ヴァグラント」が8月19日に開幕する。これまで数々のポルノグラフィティの楽曲の歌詞を手掛け、さらには小説を2作出版するなど、言葉を使ったクリエーティブの才能が高く評価されている新藤。本作では、大正時代の炭鉱を舞台にした物語と、20曲以上の楽曲を書き下ろして壮大なミュージカルを作り上げる。新藤にミュージカルへの思いや本作の楽曲についてなどを聞いた。

-ミュージカルを制作するに至った経緯を教えてください。
2019年にポルノグラフィティ(以下、ポルノ)の20周年の東京ドームでのライブが終わった後、休みがあったのでロンドンに1カ月ぐらい滞在していたんです。そのときに気まぐれでたまたま見つけた劇場に入り、「メリー・ポピンズ」を見たんですよ。英語の勉強になるかなぐらいの軽い気持ちで見たのですが、その作品がとにかく素晴らしかった。英語はよく分からないけれども、僕が好きなエンターテインメントが詰まっていて、時間を忘れさせてくれたんです。それで、改めてミュージカルはすごいと感銘を受けたのがきっかけでした。僕は、曲も書けるし、小説も書いたことがあるから物語も書ける。それなら、ミュージカルも作れるのではないかと。
-そうしてこのプロジェクトがスタートしたのですね。本作では、ある炭鉱の街にやってきた“マレビト”と呼ばれる芸能の民と村の若者が交流をしたことから、坑夫たちを巻き込んだ物語が展開していきますが、そうしたストーリーはどこから発想したのですか。
炭鉱の光景を水彩画で描いた“炭鉱絵師”の山本作兵衛さんの作品から刺激を受けました。最初はお孫さんにその当時の様子を伝えるために描かれた物だったそうですが、炭鉱労働者たちの生活をリアルに描いていて、すごくカラフルで素晴らしい作品です。その山で行われた祭りの話もたくさん描かれているのですが、色彩が華やかなのでファンタジーに感じるんですよ。その世界観が面白いなと思ったのが最初でした。
-今回、20曲以上の楽曲も書き下ろしているそうですね。
アルバム1枚以上なので、かなりの量です。初めはミュージカルを見たときに好みだった楽曲を参考に曲を作ろうと思っていたのですが、スタッフの方から「いつも晴一さんが作るような曲も聞きたい」という話があったので、普段、ポルノで書くような楽曲も作りました。そうして作ったものを演出の板垣(恭一)さんと相談しながら当てはめていくという流れでした。
-ミュージカルだからと、作曲方法を変えたということではない?
そうですね。とにかくいろいろな楽曲があります。いつもと同じように作った曲もあれば、シーンに合わせて作ったという曲もあります。ミュージカルの場合は、どうしても歌詞で伝えなければいけないこともあるので、そのためにメロディーを変えることもありました。普段、ポルノの曲は、メロディーが先にあって、そのメロディーを生かすための歌詞を何とか書こうとするのですが、ミュージカルの場合は歌詞が大切なので、普段よりも、よりフレキシブルに書いた感覚があります。
-そもそも、作曲するときは、ピアノに座るなどして意識して作るのですか。よく「降りてくる」と言いますが、そうしたひらめきを大切にしているのですか。
(降りてくると)よく聞きますが、ないですよ、そんなこと(笑)。実際にそうやって曲を作れる人なんて、ブルーノ・マーズやジャック・ジョンソンぐらいしかいないんじゃないですか(笑)? 彼らも本当に降りてきているのかは分かりませんが、少なくとも僕はない。鍵盤とパソコンに向かって作ります。ポルノの場合は、ポルノの世界観を突き詰めるために楽曲を選んでいますが、今回はこの作品の世界観に必要なら、アイドルのような楽曲もブルースも演歌も作ろうと思っていました。
-新藤さんがポルノでデビューしてから9月で25年になります。ここにきて新しいことに挑戦することについては、どんな思いがありますか。
確かに大きな挑戦ではありますが、それはやらせてもらえる環境があって、こうして舞台を制作するチームがいるからこそできることです。自分もポルノでいろいろな経験をさせてもらい、デビュー当時と比べてスキルも上がったと思いますし、受け入れてもらえる状況ができた。僕がこじ開けてこの挑戦をしているというよりは、恵まれた環境がそこにあったからというイメージです。やれる環境があるのにやらないのは失礼だと思ったんですよ。