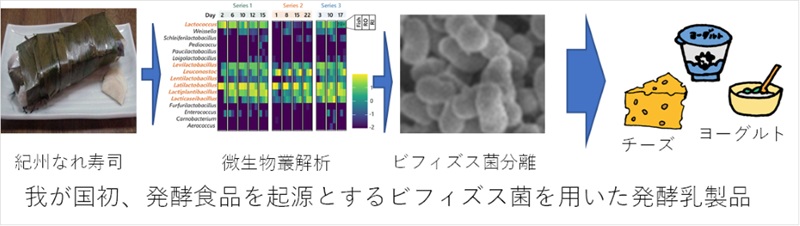発酵を通して日本各地に伝わる暮らしや風土、文化に触れる「発酵ツーリズム」を提唱する小倉ヒラクさんが11月2日、ヒルトン大阪(大阪市北区)で開催された共同通信きさらぎ会で講演した。

■繊細な麹カビから生まれた日本の食文化
“発酵デザイナー”を名乗る小倉ヒラクさんは、発酵文化を紹介する出版物、ワークショップやイベント開催などで、発酵ムーブメントを盛り上げてきた人物だ。そもそも「発酵」について、古代の人は「死んだ魂が再生していくこと」と重ね合わせて見ていたという。「お酒を発酵する酒つぼを棺として使っていた時期もある。死んでしまった魂が発酵してまた戻ってくるように願いを込めていたという話もある」。

日本を代表するしょうゆやみそ、酒などの発酵食造りは、こうじ造りから始まる。こうじとは、穀物にこうじカビを繁殖させたもので、発酵過程に欠かせないものだ。こうしたこうじ造りの原型は1000年以上前に遡ることができ、「日本の発酵技術のシンボル的なもの」だという。というのも日本では、世界でも類例を見ない高度な微生物培養が行われていることを、アジアの調査を通して知ったからだと話す。
「海外のこうじ菌は強くて他の菌に負けないのでどこででも育つが、日本のこうじカビは繊細なため、各蔵ではこうじカビを育てるための培養室を作って大事に育てている。こうじ自体は中国やインドネシア、インドにもあるが、こうじを育てる部屋があるのは日本だけ」。今の日本酒やしょうゆ、みそといった繊細な味わいは、繊細なこうじカビがあってこそ花開いた「独特の食文化」だったのだ。「たまたま弱い微生物が住んでいたために、その微生物をうまく飼い慣らす技術を発達せざるを得なかった。そういう意味で、日本は恵まれた国というより、難しい状況を克服していく中で、他の国にはない独特の技術を獲得していったといえる」

さて、ここからが本題。小倉ヒラクさんは、およそ2年かけて47都道府県71カ所を調査収集してローカルの発酵文化を収集してきた。その中で、現地の人でも知らないような発酵食の存在を知ったという。活動は地道だ。「集落の人に話しかけて面白い発酵食を聞き出し、その家に上がり込んで作っている様子をレシピに書き留める」―。聞き取りを続けるうちに、その土地の持つ「歴史や文化、精神性」と「発酵食」が深く関わっていることに気付かされていった。ここでは、その一部を紹介する。

■秋田県八森町の「ハタハタ寿司」「しょっつる」
日本海で捕れるハタハタを発酵させたのが「ハタハタずし」だ。回遊魚のハタハタは年に2週間ほど、近海に大量に集まってくる。食べ切れない量だったため、発酵させて保存食にした。
「おすしは“握る”ものというイメージがあるが、100年前くらいまでは“漬ける”といっていた」そうで、「ハタハタすし」は、おすしが「発酵食品だった名残」を感じさせる代表的な食べ物だという。
このハタハタは調味料としても使われてきた。ハタハタを塩漬けにしてドロドロに溶かした上澄みである魚醤(ぎょしょう)の「しょっつる」だ。「地元のお母さんたちに聞くと、八森は町から離れた貧しい漁師町で、なかなかしょうゆが買えなかった。それで、昭和の終わり頃まで、味付けを“しょっつる”でしていたとか」。高度成長期以降、日本の食文化が一気に画一化したことも、食文化の聞き取り調査で痛感したことだ。「今では当たり前に使っている調味料が使えていなかった。発酵文化を見ていると、現代人が当たり前に思っているものが、そうではなかったことが分かる」。


■愛知県岡崎市の「八丁みそ」
東海地方で愛される八丁みそは、実は「全く日本の調味料っぽくないもの」だという。どちらかというと「中国の調味料の豆豉(トウチ)」に近い。豆豉とは、大豆や黒豆を発酵させた塩味の強い調味料で、麻婆豆腐などの中華料理に使用されている。
「中国の人は甘酒など甘酸っぱい感じが苦手。でも八丁みそのような苦くて渋いものは好き。逆に日本人は、苦味やえぐみが苦手」。その味覚の違いから、「当初、みそは(大陸から)豆豉のようなものが入ってきたが、日本ではもっと軽やかで甘酸っぱいものが好まれるため、米や麦を入れて今の軽やかなみそになった」という。
ところが八丁みそは、「大陸由来の大豆だけを発酵させた苦味のあるみそを作り続けている」というのだ。一体なぜ、日本人には受け入れられにくい味が、この土地にだけ残ったのか。その疑問には、衝撃の答えが返ってきたという。「徳川家康が変な食生活をしていたらしくて。八丁みそもめちゃくちゃ大好きだったらしい。徳川家の家訓によって、大事にされて守られてきたようだ」。
八丁みその事例を見ると、人間の味覚は、「生理的な欲求」だけでなく、「文化的な好み」にもかなり影響されていることが分かる。「東京の人が八丁みそを飲むと“?”となる」が、「愛知県岡崎市は、一般的な日本人が好きでない味を飲んできているので、おいしい」と思う人が多い。つまり、八丁みそこそ「文化的な好み」が強く反映された食べ物の典型といえ、「味覚は文化」でもあることを示しているのだ。


■新潟県妙高市の「かんずり」
大寒の日、雪原にまかれる赤い唐辛子。雪に埋もれてしばらくするとシナシナになり、そこにこうじを入れて発酵させてつくられるのが、辛味調味料の「かんずり」だ。新潟県妙高市のソウルフードである。
「江戸時代、新潟は医療の手が回らず、薬草を食べて病気を予防する文化(本草学)があった。唐辛子は当時の薬で、唐辛子でかんずりを作って食べ、病気にならないようにしていた」。「かんずり」は、まさに「先祖の知恵」がなし得た発酵食だといえよう。こうした医療の手が回らない山間部や島で発達した発酵文化、伝統的な発酵食を解析していくと、「健康機能の高い物質がいっぱい出てくる」のだという。


■東京都伊豆諸島南部青ヶ島の「青酎」
八丈島のさらに南にある人口160人程度の小さな火山島、青ヶ島。火山の斜面に椿畑を作る特徴的な地形を成し、噴火で水源が枯れて田んぼが作れなかったため、人々は麦とサツマイモを食べて暮らしてきた。そこで生まれたのが、麦とサツマイモで作る不思議な焼酎、青酎(あおちゅう)だ。
「こうじを作るときは、工場で培養されたカビを使う」のが一般的。カビは、一歩間違えると毒にもなるからだ。「ところが青ヶ島では、今でもそこの島にいる菌でお酒を醸すという不思議なことをしている」。「青酎」に使う麹は、溶岩に生える熱帯植物タニワタリの葉っぱの裏に住む黒カビを移して作る。その理由は、歴史をひもとくことで明確になった。40年前まで4カ月に1本しか連絡船がなく、島外から何も持ち込むことができなかった。そのため、「自分たちで作る、楽しみとして作る、島のものだけを使って作る」ことが当たり前だったのだ。こうした、あるものを使う精神は、「日本の醸造文化の原点」だという。


■福井県小浜市の「鯖のなれずし」、富山県朝日町蛭谷の「バタバタ茶」
北陸の食文化の特徴は、「精神性の高い食べ物が多い」ことだという。福井県小浜市の「鯖のなれずし」は、ぬかに漬けた後にさらにお米に漬けるため、出来上がりまでに1年半もかかるという大変手間のかかった食べ物だ。もともとは正月の神饌(しんせん・神様への供え物)で、人々はそのお下がりを食していた。若狭には、その土地で生まれたおいしいものを偉い人に献上する文化があり、それが御食国(みけつくに)とも呼ばれている所以だ。
富山県朝日町蛭谷(びるだん)の「バタバタ茶」は、発酵の旅で最も衝撃を受けた食文化の一つだという。硬くて緑茶にできない遅摘みの茶葉を微生物でむりやり解体分解して作られた、日本にほとんど類例が見られない発酵茶で、抹茶のように点てて飲む。この不思議なお茶は、布教活動から生まれた。「北陸で浄土真宗を布教した蓮如上人(室町時代の僧)が蛭谷を尋ねた時、“仏の話をしよう”では誰も集まってこなかったので、“みんなでお茶を飲もう”と言って人を集めた」と言い伝えられている。
その文化がおよそ600年続き、今でも月命日には集落の人々が集まって故人を偲び、バタバタ茶を飲む。古くから根付く精神性や信仰が、町場の人々が親しむ発酵食として残された事例だ。「発酵をたどることで、日本人がどのように生きてきたのか。何を大事にしてきたのか。その土地がどのように成り立ってきたのかが見える。その土地ならではの価値が、発酵食の中に詰まっている」


■世界から注目され始めた日本の発酵文化
日本と世界各地のフィールドワークに自らのデザイン力を掛け合わせた出版物を手掛け、2019年にキュレーターを務めた「発酵ツーリズムにっぽん」展(渋谷ヒカリエ)には3カ月で5万人が来場した。2020年には、東京・下北沢に発酵専門店「発酵デパートメント」をオープンさせ、「発酵の聖地」として注目を集めている。
2022年、福井県から「地域のためになるプロジェクトを」と声が掛かり、「展覧会と旅が合体」したユニークなプロジェクトを立ち上げた。現在開催中の「発酵ツーリズムにっぽん/ほくりく」(12月4日まで)は、会場である金津創作の森美術館(福井県あわら市)をチェックイン場所として北陸各県にサテライト会場を用意し、そこで実際に醸造家の話を聞き、発酵食を味わうことができるという異色の展覧会だ。展覧会に合わせて、発酵の視点で北陸を旅する旅行ツアーも組まれている。
すでに開催した海外向けツアーでは、アメリカからミシュランシェフも参加した。日本の伝統的な発酵文化は、和食の神髄として、早くも海外から注目され始めている。
「毎日インド、北欧、アメリカとか、いろんな国から連絡が来ている。日本の人たちが発酵文化の価値をどこまで再認識してくれるかは分からないが、その前に海外の人がもう気付いている」
発酵デザイナーという肩書きで、やろうと思っていたことのほとんどを実現したという小倉ヒラクさん。「これから、この発酵文化を人類の共有財産にしていくことが、僕の次の仕事のマイルストーンになると思う」と締めくくった。



阪神梅田本店で開催中の「発酵ツーリズム にっぽん/ほくりくマーケットin阪神」で11月6日(日)、書籍『発酵ツーリズムほくりく』発売を記念したトークショー&サイン会を開催予定(定員20人、参加費1000円)。「発酵ツーリズム にっぽん/ほくりくマーケットin阪神」は11月7日まで。
小倉ヒラク
83年東京生まれ。早稲田大学文学部で文化人類学を学ぶ。企業デザイナーとして活動後、東京農業大学研究生として発酵学を学ぶ。47都道府県を旅して日本のローカル発酵文化を発掘し、全国の醸造家たちと商品開発やワークショップを開催している。絵本&アニメ「てまえみそのうた」でグッドデザイン賞2014受賞。『日本発酵紀行』(2019年)、『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』(2020年)他。